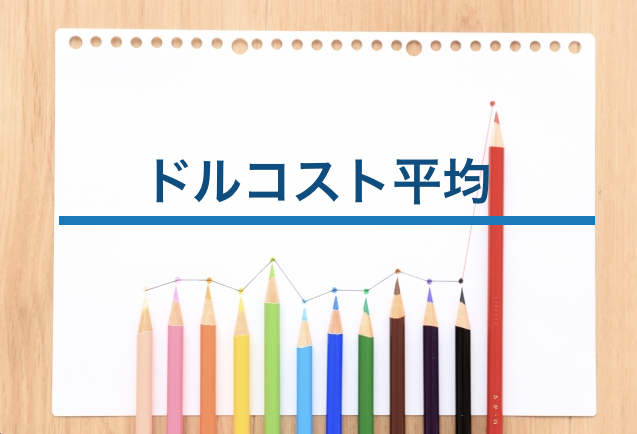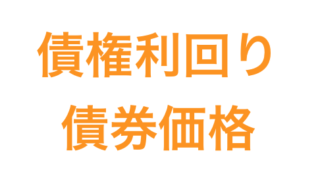資産形成の基本として語られることが多い「ドルコスト平均法」。
つみたてNISAやiDeCoなど、身近な制度にも活用されている投資手法です。
「毎月決まった額を積み立てれば、長期でリスクが下がる」
「初心者はドルコスト平均法から始めるべき」
――こうした説明を聞いたことがある方も多いでしょう。
しかし、ドルコスト平均法には「気休め」にすぎない側面もあります。
制度のメリットだけを信じて投資すると、思わぬ落とし穴にはまることも。
本記事では、2025年の最新情報をもとに、
-
ドルコスト平均法の基本
-
メリットと誤解されやすい点
-
本当のデメリットと注意点
-
社員持株会との危険な相性
まで徹底的に解説します。
ドルコスト平均法とは?基本をおさらい
ドルコスト平均法(Dollar Cost Averaging)とは、
「一定金額を、定期的に、同じ金融商品に投資し続ける方法」
を指します。
たとえば、毎月5万円ずつeMAXIS Slim 全世界株式を買い続けるようなケースが該当します。
価格が高い月には少しだけ、安い月には多く買うことになります。
この手法は、特に以下のような制度でよく使われています。
-
つみたてNISA(毎月の積立設定)
-
iDeCo(給与天引きで定額積立)
-
企業型確定拠出年金
-
社員持株会
投資初心者が入りやすい制度とセットになっているため、自然とドルコスト平均法が採用される仕組みになっています。
ドルコスト平均法の3つのメリット
① 高値掴みを避けられる(平均購入単価が平準化)
相場が上下するなかで、毎月定額を投資することで、高い時には少なく・安い時には多く買えます。
このため、購入単価が平均化され、「高値掴み」を防ぐ効果があるとされます。
② 投資判断に悩まずにすむ
毎月自動的に買い付ける仕組みなので、「いつ買えばいいのか」と迷う必要がありません。
感情に左右されず、淡々と投資を続けることで、暴落時にも継続しやすい点が特徴です。
③ 時間分散によるリスク軽減
一括で投資するよりも、時間を分けて投資することで、「投資タイミングによる偏り」を抑える効果があるとされています。
でも本当に有利?ドルコスト平均法の「落とし穴」
結論から言うと、ドルコスト平均法には過剰に期待すべきではありません。
なぜなら、以下のような弊害や誤解があるためです。
① 「得をするわけではない」
「高値では少なく、安値では多く買える」という構造があるため、一見得しているように感じます。
しかし、リターンが大きく改善するわけではありません。
長期で見れば、最終的な成果は「どの資産に、どれだけ投資したか」で決まります。
購入単価が平準化されても、それが運用成果を劇的に改善する保証はありません。
② 機会費用の損失
たとえば手元に300万円あるのに、それを30カ月に分けて月10万円ずつ積み立てるとします。
この場合、実際に300万円がすべて投資されるのは2年半後。
その間、投資していない分の資金は「運用機会を失っている」ことになります。
このような状態を「機会損失」と呼びます。
特にインフレ時代には、現金を寝かせること自体がリスクになり得ます。
③ 分散投資にはならない
よく「ドルコスト平均法はリスク分散になる」と言われますが、これは誤解です。
時間的な分散にはなりますが、資産の分散にはなりません。
例えば毎月S&P500連動のファンドだけを買い続けていれば、米国市場に集中投資していることになります。
分散というには「異なる資産クラス」や「地域」「業種」などの幅が必要です。
社員持株会は危険?ドルコスト平均法の落とし穴が顕著に出る例
社員持株会は、給料から一定額を天引きして自社株を購入する制度です。
一部の企業では「5〜10%の奨励金」がつくなど、一見お得に見えるかもしれません。
しかし、この仕組みには重大なリスクがあります。
ダブルパンチのリスク
もし会社の業績が悪化し、株価が下がり、さらには給与カットやリストラが行われたら――。
-
収入(給料)が減る
-
資産(自社株)も減る
というダブルパンチを受けることになります。
これは「収入と資産が同じ会社に依存している」ことによる構造的なリスクです。
社員持株会=分散投資と真逆の行為
繰り返しになりますが、同じ会社の株を積み立てることは「集中投資」そのものです。
そのため、どれだけ毎月コツコツ買っていたとしても、分散投資とは程遠い構造になっています。
企業から配られる案内パンフレットには「ドルコスト平均法でリスクが軽減される」と書かれているかもしれません。
しかしそれは、ごく一部の側面だけを切り取った説明にすぎません。
つみたてNISAやiDeCoでのドルコスト平均法はアリか?
ここまでドルコスト平均法の課題を述べてきましたが、つみたてNISAやiDeCoでの活用は理にかなっています。
なぜなら、
-
給料の中から毎月積立するしかない(まとまった資金がない)
-
自動で非課税枠を使い切る仕組みになっている
-
長期的な資産形成に向いている
からです。
ただし、以下の2点には注意してください。
投資先は分散されたインデックスファンドにする
たとえば、
-
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
-
SBI・V 全米株式インデックスファンド
などの、低コストで分散性の高いファンドを選びましょう。
毎年の資金余力に応じて「一括投資」を使い分ける
たとえばボーナスが入ったタイミングや、資金に余裕があるときは、一括で投資する選択肢も併用すると、機会損失を減らせます。
まとめ|ドルコスト平均法は「使い方次第」。過信は禁物
ドルコスト平均法は、感情に左右されずに長期投資を継続しやすいという点で有効です。
つみたてNISAやiDeCoといった制度とも相性が良く、多くの投資初心者にとって「入り口」として最適でしょう。
しかし、以下の点を忘れてはいけません。
-
期待リターンが向上するわけではない
-
資金があるなら一括投資の方が効率的
-
分散投資とは別の話である
-
社員持株会との併用はむしろリスクになる
ドルコスト平均法は「リスクを完全になくす魔法の手法」ではなく、「長く投資を続けるための補助輪」のような存在です。
制度や仕組みに依存するのではなく、自分の資金状況・投資目的・リスク許容度に応じて使い方を選びましょう。
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。