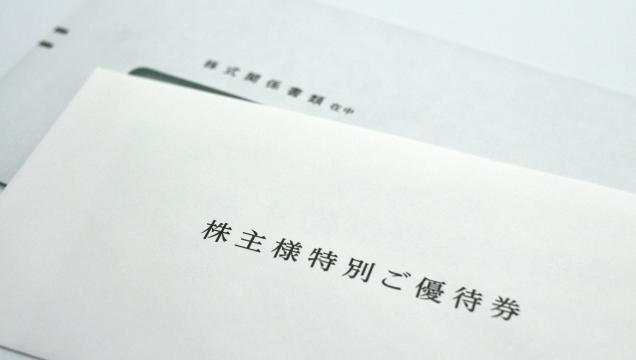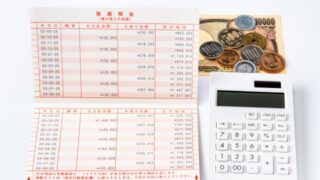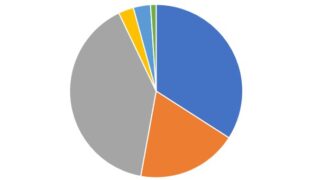「投資信託で過半数が損をしている」は誤解?
ある報道で、「投資信託で過半数の人が損をしている」という見出しが注目を集めました。しかし、これは金融庁の公表内容を正確に反映したものではありません。
金融庁は、かねてより、銀行のあまりに営利的な勧誘営業を批判してきましたが、今回は、銀行(投信を販売する金融機関)に対して、顧客の運用損益や投信のリターン実績を公表することを求めました。
その伏線として、冒頭の「半数が損」説を流したのです。「貴行が顧客本位であるなら、実績を公表してみろ」というワケですね。
◆調査結果が生む3つの憶測
この「半数が損」説は、さまざまな憶測を生みそうです。
1. 投信とは、もうらからない商品?
2. 銀行は、もうからない投信を売っている?
3. 個人は、もうからない運用をしている?
1つの結論だけですべてを判断してしまうのは、思考停止です。1つの数字から典型的なパターンしか想像できないのは、想像力の欠如であり、だまされやすい人であることの証明です。あなたはこの発表を見て、どう解釈しましたか?
◆300人の投資実績は?
先ほどの憶測が間違っているという反証を、書かせていただきます。私が知っている300人以上の個人投資家の実態です。
1. 投信を長期積立で買って、損をしている人はほぼいない
2. 13年も毎月購入を続けている人の運用利率は年7.5%
3. 良い投信を、2倍3倍に増えるまで保有し続けている
同じ投信を買っているのに、何が違うのでしょうか?
◆金融庁調査が誤解される理由は?
前述の銀行顧客の個人投資家は、投信の保有が1~2年と短いです。したがって、少し利益が出ると、すぐに売ってしまっているということが想像できます。
ということは、保有中の含み益が少ないので、今回の調査では、良い成績として捕捉されていません(たとえ、増える投信を買ったことがあったとしても)。持っているのは、塩漬け銘柄ばかりという実態だからです。
そもそも、投信という商品に罪はありません。どんな商品にも、ダメなものと優れたものがあります。「半数が損」というひどい発表から、個人的な憶測で、軽々に結論を導き出すのは誤解の元です。銀行が悪いのか?投信が悪いのか?という、安直な犯人探しをしてしまいがちだからです。
出典:あるじゃん(All About マネー)
実際には、金融庁が全国の都銀・地銀29行を対象に、各行の顧客に対してどれだけの投資リターンを提供できているかという「成果指標(KPI)」を公表したものです。この事実をもとに、一部メディアが「投信で損をしている人が多い」と報じたのが実情です。
もちろん、金融庁が金融機関の営利優先の姿勢に対して問題意識を持っていることは確かです。だからこそ、KPIの公表に踏み切ったのでしょう。
金融庁:投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて
個人投資家300人の声は偏りがある?
今回取り上げたブログ記事では、「私の知っている300人以上の個人投資家の実態」として、投資信託で利益を得ている人がいると紹介されています。
しかし、この記事を書いた方は高学歴で金融知識も豊富と見られ、その交友関係にはバイアスがある可能性が高いです。知識のある投資家たちと、銀行で勧められるまま投信を購入した高齢者や初心者では、当然ながら結果も大きく異なります。
また、「投資信託の保有期間が1~2年と短く、利益が出たらすぐに売ってしまう傾向がある」といった記述もありますが、これは想像の域を出ないコメントであり、読者に誤解を与えかねません。
銀行の営業に頼るのは危険
投資信託そのものが悪い商品というわけではありません。ただし、「銀行で販売されている投資信託」には注意が必要です。
銀行の営業マンは「金融の専門家」ではなく「販売のプロ」です。信頼できるように見えても、実際には手数料収入を目的とした営業が多く行われており、知識のない高齢者や初心者が損をするケースが後を絶ちません。
このような背景から、金融庁はiDeCoやつみたてNISAにおいて商品ラインナップに制限を設けたのです。もし規制がなければ、老後の資産形成の名のもとに、高コストな商品が販売されていた可能性もあったでしょう。
実際、私の身近にも銀行の投資商品で損をした人がいます。繰り返しになりますが、銀行で購入して良い投資商品は、せいぜい個人向け国債程度です。投資を始めるなら、ネット証券を活用し、信頼できる情報を自分で得て判断するべきです。

まとめ:投資で信頼すべきは「商品」より「手段と経路」
-
金融庁は「投信で損をしている人が多い」と断定したわけではない
-
投資で利益を得ている人の声にはバイアスがある可能性が高い
-
銀行で販売される投信は、高コストで顧客本位ではないことが多い
-
投資で本当に注意すべきは「商品」よりも「購入経路と営業トーク」
投資で損をしないためには、他人に頼らず、自分で正しい情報を得て判断する力が必要です。特に、銀行の営業トークには要注意。できるだけネット証券を活用し、自衛する姿勢を持ちましょう。
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。