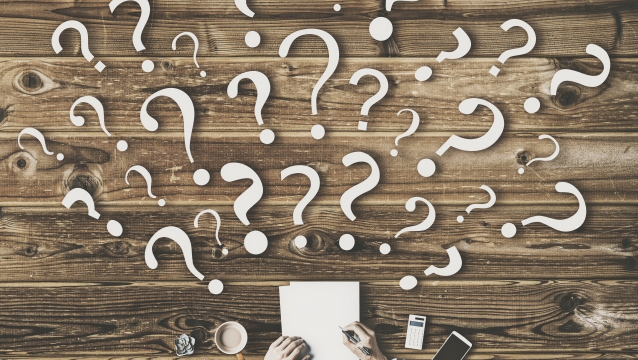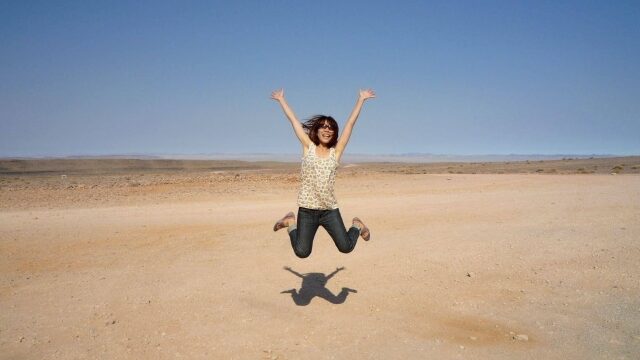50代の平社員として長年会社に勤めてきました。組合費を払う一方で、現場の実感として「この仕組み、今の時代に合っているのか?」と首をかしげる場面が多い——それが正直な気持ちです。この記事では、最新データと私の実体験をまぜて、労働組合の存在意義を“2025年の今”の視点で考え直します。
結論|「組合は要らない」ではなく「今のままでは機能しない」
組合は、個が交渉力で劣る場面で大切なセーフティーネットです。ただし、昭和型の運動様式を引きずれば、現場に効く成果は生まれません。私は「現場接続」「非正規の包摂」「政治活動の透明化」の3点を欠いた組織は、やがて支持を失うと感じています。
最新データで見る“縮む組合”とレアになったスト
厚労省「労働組合基礎調査」では、2024年の推定組織率は16.1%。3年連続で過去最低水準を更新しました。組合員は約991万人と減少する一方、女性やパートの組合員は増えています。現場にとっての意味は「カバー範囲の狭まり」と「属性の多様化」です。(厚労省調査)厚生労働省日本法令外国語翻訳ガイド
一方で、ストは“ほぼ失われた権利”ではありません。2023年のそごう・西武のストは、百貨店で61年ぶりとして象徴的でした。だからこそ大きく報じられたとも言えます。争議件数自体は長期では低位ですが、2023年は総争議292件・参加10.1万人に増加しました。(参考)Reuters Japan厚生労働省
なぜ組織率は下がるのか(私の理解)
1)産業構造の変化:製造業の比率低下とサービス化で職場が分散し、企業別組合が機能しにくい。
2)雇用の多様化:非正規・副業・業務委託が増え、従来の“社員=組合員”モデルが合わない。
3)価値観の変化:賃上げだけでなく、柔軟な働き方・健康・学び直しなど、要求の幅が広がった。
“強制加入”という言い方の落とし穴(ユニオンショップの現在地)
日本の企業別組合ではユニオンショップ協定が残っています。実務上は「入社したら加入が前提」という空気になりがちですが、法的には限界があります。
最高裁は、他の労働組合に加入している人、または脱退後に他組合へ加入・新設した人にまで解雇義務を及ぼす条項は公序良俗違反で無効と判示しています。(最高裁判決の要旨)裁判所+1
つまり、会社や組合の運用が“なんとなく”で強すぎる同調圧力を生むなら、それは法の想定外です。私たち労働者側も、仕組みの正確な射程を知っておく必要があります。
非正規と個人をどう守るか:組合の外にもルートはある
正社員中心の企業別組合では、同じ職場の非正規が取り残されることがあります。ここは2021年以降も変わりにくい現実です。
とはいえ、個人や非正規でも入れる地域・合同ユニオン、都道府県労働局の総合労働相談・あっせんなど、組合の外にある救済ルートは整っています。総合労働相談は直近でも120万件超で高止まり。現場の悩みは“見えない場所”で積み上がっています。(厚労省データ)厚生労働省+1
私の現場の違和感(具体例)
・正社員側はボーナス交渉を重ねる一方、同じ売場の非正規はそもそも対象外。説明の場にも呼ばれない。
・議題が毎年ほぼ同じ。会議体のための会議になっていて、改善のKPIが示されない。
・育児や介護の柔軟な働き方は“個別対応”で終わり、制度として横展開されない。
政治活動の距離感:現場の理解を得るために“見える化”を
政策実現のために政治と関わる——これは労働組合の公式方針として位置づけられています。暮らしを左右する税・社会保障・雇用ルールは政治の領域にあるからです。
ただし、現場の関心から離れたイシューに傾けば「思想の押し付け」と受け止められ、逆効果になります。支出や意思決定のプロセス、支援対象の選定基準を“見える化”すること。
50代平社員の実感:組合費の“リターン”をどう測るか
私の評価軸はシンプルです。
「①賃金・労働時間・休暇で具体的改善があったか」
「②非正規や外注まで含めた現場の不公平を減らしたか」
「③説明責任を果たしているか」
この3点が揃えば、毎月の組合費は“投資”になります。逆に、前年踏襲の議題とセレモニーだけなら“固定費”に感じます。あなたの現場でも、同じ物差しで一度点検してみてください。
いま組合に求めたいアップデート(提案)
1)現場接続:専従任期の上限やローテを導入し、一定期間ごとに“現場に戻る”設計にする。
2)包摂の再設計:非正規・請負・アルバイトの声を拾うため、職場横断の合同ユニオンと連携し、企業別の“囲い”を越える。
3)政治の透明化:支援対象・費用・意思決定の根拠を年次レポートで公開。現場アンケートで優先イシューを決める。
4)成果の見える化:春闘以外でも、時短・健康・安全・ハラスメント対策などKPIを四半期で報告する。
個人が今日からできること(会社員×投資家の目線)
・まずは就業規則と労働協約を読む。自分の職場のルールを知らないと不利益に気づけません。
・困ったら“早期相談”。会社の外(総合労働相談・合同ユニオン・弁護士)も並行であたる。
・交渉テーマは「数字化」。残業時間、年休取得率、評価分布など定量で詰めると前に進みます。
・投資家の視点も忘れずに。人件費削減だけでは持続的成長は続かない。適正賃金は企業価値の土台です。
まとめ|『現場×包摂×透明性』で、組織はもう一度強くなる
労働組合そのものは、これからの時代も必要です。問題は、やり方の古さ。最新データが示すのは“組織の縮小”と“現場の多様化”です。
組合が現場と再接続し、非正規を包摂し、政治活動を透明化できれば、組合費は「固定費」から「未来への投資」に変わります。私自身も、その変化を期待し、現場から声を上げ続けます。
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。