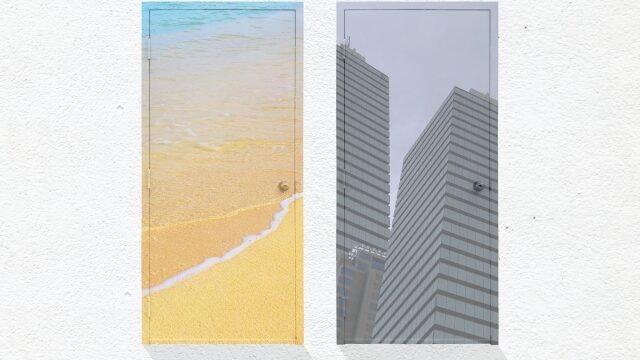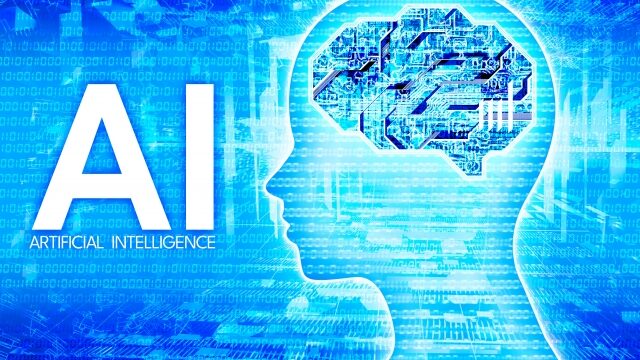アベノミクスが政権政策としてスタートしてから10年以上が経過し、日本経済は株価上昇や円安進行、企業収益の改善など「マクロの数字」で見れば確かに変化を遂げてきました。
しかし、私のような賃貸暮らし・50代サラリーマンの立場から見ると、「景気はよくなっている」という声と「生活はまだ楽になっていない」という実感が交錯しています。特に中間層には、「数字の好転」が生活の安心や余裕につながっていない場面が少なくありません。
この記事では、最新データをもとにアベノミクスの効果と限界を整理し、中間層の暮らしに焦点を当てます。
1. 名目賃金は上昇、しかし実質賃金はマイナス続き
まず、賃金動向をデータで確認してみましょう。2025年の春闘では、大手・中小ともに賃上げ率が5%前後と報告され、名目賃金は確かに上昇しています。実際、毎月勤労統計でも一般労働者の所定内給与は前年比+2.4%増と堅調です。
しかし問題は「実質賃金」です。2025年6月時点で前年同月比マイナス0.8%、5月はマイナス1.7%と、5か月連続で減少しました。要するに、物価上昇が賃金上昇を上回り、生活実感が追いついていないのです。
私自身も給与明細を見れば「上がっている」ように感じるのに、家計簿をつけると光熱費や食費に押されて余裕がなくなることが何度もあります。
2. 最低賃金引き上げは低所得層には追い風
アベノミクスの流れを受け、最低賃金も大きく引き上げられてきました。2025年度の全国加重平均は1,121円となり、過去最大の引き上げ幅(+66円)です。東京都では1,226円、神奈川県では1,225円と、首都圏の水準は全国トップクラスになっています。
この水準は、アルバイトやパートなど非正規雇用者にとっては朗報です。かつて900円台が当たり前だった時給が1,200円前後になれば、生活の下支えになります。
とはいえ、中間層にとっては最低賃金の直接的恩恵は限定的で、むしろ「物価も上がっているのに家計全体の余裕は変わらない」という声のほうが多いように感じます。
3. 中間層が実感を持てない理由
では、なぜ中間層には「景気がいい」という実感が薄いのでしょうか。いくつかの要因を整理します。
(1) 物価と固定費の上昇
食料品、光熱費、ガソリン、通信費といった日常必需品の価格が軒並み上がっています。名目賃金が3%伸びても、生活コストが5%上がれば実感としてはむしろ苦しくなります。特に賃貸暮らしでは家賃負担が重く、関東圏では10万円を超えることも珍しくありません。
(2) 非正規雇用・短時間労働の不安定さ
時給が上がっても、週に働ける時間数やボーナス・手当がつかないと年収ベースでは大きな改善になりません。
(3) 税・社会保障負担の増加
消費税や社会保険料の負担増が続いており、可処分所得は目減りしています。名目の賃上げ分がそのまま手取りに反映されにくい構造も実感を阻む要因です。
(4) 企業の生産性格差
大企業や輸出産業は好業績で賃金を上げやすい一方、中小企業やサービス業は人件費上昇が直撃します。人を雇う余裕がなく、結果的にセルフレジや無人店舗などの機械化に頼らざるを得ない現実があります。
4. モデル世帯シミュレーション:横浜市で暮らす中間層
具体的に関東圏の中間層家庭をシミュレーションしてみます。
「50代サラリーマン(年収600万円)、妻は専業主婦、中学生の子ども1人、横浜市で賃貸暮らし」というモデルです。
-
手取り月収:約42万円
-
家賃:約11万円(中区1LDK〜2DK相場)
-
光熱・水道・通信費:約2.8万円
-
通勤・交通費:約1.5〜2万円
-
食費:約6〜8万円(家族3人)
-
教育費:約1.5〜2万円
-
保険・医療費:約1.5万円
-
交際・レジャー:約2万円
合計で月の支出は27〜30万円。残りの可処分所得は12〜15万円程度です。この余裕から老後資金の積立や突発出費に備えるわけですが、正直に言えば「十分な余裕」とは言いにくい。物価がさらに上がれば、すぐに削られてしまう額です。
5. 富裕層と低所得層にはプラスの側面も
中間層に実感が薄い一方で、恩恵を受けている層も存在します。富裕層は株式や不動産価格の上昇で資産が増え、低所得層は最低賃金引き上げで時給が底上げされました。とはいえ、これが「生活の安定」や「将来への安心」につながっているかは別問題で、まだ道半ばと言えます。
6. これから求められる政策と個人の工夫
今後、景気を「実感」に変えるには次のような施策が重要でしょう。
-
中小企業への賃上げ支援や生産性向上策の強化
-
税制や社会保障制度の見直しで中間層の負担軽減
-
地方と都市の生活コスト格差を縮める取り組み
-
雇用の安定化と非正規から正規への道筋の拡充
一方で、個人ができることもあります。スキルアップや副業による収入源の複線化、固定費の見直し、そして長期的な投資による資産形成です。
私自身も新NISAを活用してインデックス投資を続けることで、労働収入に依存しない“資本家側”の視点を少しずつ取り入れています。
7. 結論:数字だけでなく“感じられる好景気”を
アベノミクスは確かに成果を残しました。株価上昇、企業業績回復、最低賃金の底上げ。しかし、それが中間層の「暮らしの余裕」や「安心」には十分に届いていません。名目の数字だけではなく、実際の生活コストに照らして改善が見えるような政策が不可欠です。
私たち中間層にとって大事なのは、ニュースで聞く「景気の好転」ではなく、家計簿を開いたときに「少し余裕が出てきた」と感じられること。今後も政策の方向性と自分の家計戦略を合わせながら、数字だけでなく“感じられる好景気”を求めていきたいと思います。
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。