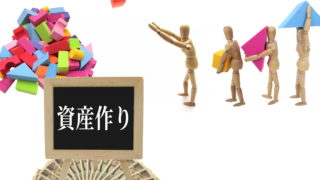最初に結論です。個人投資家の主戦略はインデックス投資だと、私は18年以上の経験から確信しています。派手さはないけれど、長く続けた人ほど成果が出る。50代・平社員の私も、相場の浮き沈みに振り回されず、淡々と積み立ててきたことで家計の不安が小さくなりました。
なぜ“市場平均”が正解に近いのか——データで確認
アクティブ運用が常に悪いわけではありませんが、長期になるほど「市場平均に負けるファンド」が多数派になります。S&Pダウ・ジョーンズのSPIVA日本(2024年年次)では、国内大型株で62%のファンドがベンチマークに劣後、5年・10年・15年では8割超が劣後という結果でした。
米国でも2024年は大型株の65%がS&P500に劣後しています。手数料や売買回転のコストが、静かにリターンを削るからです。
この“確率の壁”は、私たち個人が「勝ち続けるアクティブ」を選び続けることの難しさを示しています。だからこそ、インデックス=市場平均を低コストで取りにいく戦略が合理的になるわけです。
営業トークに振り回されない——高コストの罠
銀行や郵便局、証券の対面窓口では、手数料の高い商品が推されがちです。最新テーマや新興国、AIや半導体など「伸びそう」な言葉は魅力的ですが、コストが高いほど長期の複利が目減りします。
私自身、昔は営業トークに心が揺れた時期がありましたが、いまは「窓口でファンドは買わない」をマイルールにしています。ネット証券で低コストのインデックスに徹する——これだけで失敗の芽をかなり摘めます。
株式投資はギャンブルではない——行動バイアスに気づく
日本では「株は危険」のイメージが根強い一方、短期で儲けようとする“賭け”に近い行動が失敗の原因になりがちです。人は目先の利益を優先する現在志向バイアスを持っています。
だからこそ、相場ニュースやSNSの熱狂に煽られた時ほど、一歩引いて「10年後も説明できる行動か?」と自問するようにしています。インデックス投資は“退屈”ですが、その退屈さが武器になります。
私のやり方(50代・家計重視)
2024年からは家計の支出増に合わせ、つみたてNISAの積立を月13,000円に減額しました。内訳はオルカン1万円、S&P500を3,000円。入金力が落ちる時期でも続けられる金額に落とし込み、「やめない仕組み」を優先しています。
暴落局面でもルールを崩さないよう、口座から自動で引き落とされる設定に。投資に割く思考体力を最小化し、家族時間と仕事に回します。
今日からできる3ステップ
-
目標と期間を決める(例:教育費と老後資金、15〜20年スパン)。
-
つみたて設定を作る(世界株か米国株の低コストインデックス、NISA優先)。
-
見直しは年1回だけ(家計や目標の変化を確認、商品入れ替えは最小限)。
どの指数にするか迷うなら
初心者は“迷ったら広く”が合言葉。全世界株(オルカン系)は国や業種の入れ替わりに自動追随し、米国株(S&P500系)は世界の利益創出の中心にベットする考え方です。
私は両方を少額で組み合わせ、家計と気持ちのバランスを取っています。
コスト1%の差が、20年後の“結果”を変える
投資の世界では、目に見えにくいコストがじわじわ効いてきます。たとえば年5%の想定リターンの商品と、手数料などで実質4%になる商品。
300万円を20年運用すると、前者は約7,964,000円、後者は約6,575,000円。差は約1,389,000円にもなります。商品知識より“低コスト”という原則を守るほうが、よほど効果的です。
商品選びの私的チェックリスト
・販売会社ではなく運用会社と指数で選ぶ(例:全世界株、S&P500)
・信託報酬は年0.1%以下を目安に。隠れコスト(売買・貸株・監査)も資料で確認
・毎月分配型は原則パス(タコ足分配で元本が目減りするリスク)
・純資産残高と資金流入が安定しているか(規模の経済でコスト低下が期待しやすい)
・積み立てはNISA枠を優先、課税口座は“余裕資金のみ”
暴落とどう付き合うか——“売らない仕組み”を先につくる
相場は必ず上下します。私の基本は、
①自動積み立て、
②生活防衛資金を別口座に確保、
③スマホの株価アプリを見ない期間を作る。
この3つで「売りたくなる衝動」を弱めます。暴落時こそ“将来の収穫期に種をまけている”と考えると、気持ちが少し楽になります。
やってはいけない行動
・流行りのテーマに全力乗り(集中投資は寝不足のもと)
・高レバレッジの長期放置(想定外の値動きに心が折れる)
・営業トークだけで購入(自分の言葉で説明できない商品は買わない)
・家計の余裕がないのに積み立て増額(続かない投資は、投資ではない)
50代の資産形成は“攻めすぎない攻め”で
私自身、教育費と親の介護費が重なる世代。入金力が落ちても、積み立ての火だけは消さないようにしています。
無理な上積みをせず、家計の固定費を整える。余力が出たら積立額を少し増やす。これを繰り返すことで、資産と心の両方が安定しました。
まとめ——“退屈を続ける力”が最強
市場を当てにいくほどブレやすく、外した時のダメージも大きくなります。だから私は、流行や予想から距離を置き、低コストのインデックスを機械的に積み立てる。
家計が苦しいときは掛金を落としても、仕組みは止めない。これが50代の私にとっての“勝ち筋”でした。インデックス投資は地味ですが、長く続けた人の味方です。
10年後、ほっとできる自分のために、今日も黙って積み立てを続けましょう。
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。