50代平社員が実践する資産7,000万円の守り方
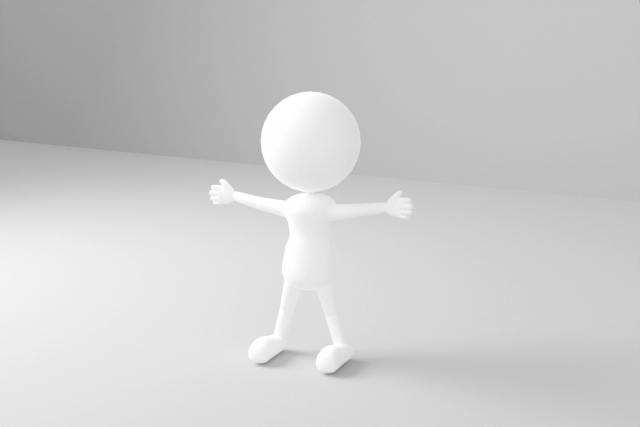
50代も後半に差し掛かると、会社では役職もなく、昇給の見込みも薄くなります。私も例外ではなく、いわゆる「平社員」のまま。とはいえ、焦りや諦めの代わりに、地味な投資を積み重ねてきた結果、現在の総資産は7,000万円台に到達しました。
収入は平均以下、ボーナスも決して多くはありません。ですが、20年以上かけて“やらないこと”を決め、“続けること”を習慣にした結果です。今回は、私が実践してきた「長期・分散・低コスト」という投資の基本を、実体験を交えて紹介します。
役職がなくても資産を築けた理由
若い頃の私は、給料が入れば使い切るタイプでした。貯金もわずかで、投資なんて遠い世界の話。しかし30歳を過ぎた頃、「このまま定年を迎えたら不安だ」と感じ、思い切って投資を始めました。
最初に買ったのは個別株の「イオン株」です。その後は個別株からETFを購入するようになりました。また、証券口座の画面をなるべく見ないようにしました。人間は“動くと負ける”生き物です。短期の値動きに一喜一憂せず、積立を機械的に続けることを最優先にしました。
その後、リーマンショックやコロナショック、ウクライナ侵攻など、市場の波に何度もさらされました。正直、不安で売りたくなった時期もありましたが、「積立をやめない」ことだけは守りました。
この「継続の力」が最終的に私を助けてくれました。株価が下がるたびに安く買えたおかげで、結果的に平均取得単価が下がり、回復時のリターンを最大化できたのです。
新NISAを軸に「分散」を徹底する
2024年から始まった新NISAでは、成長投資枠とつみたて投資枠の両方を活用しています。
主な投資先は、オルカン(全世界株式インデックス)とS&P500。日本株は個別ではなく、投信を通じて全体に広く分散する形です。私はかつて日本個別株にも手を出しましたが、決算や株主優待に振り回され、最終的にはインデックス投資に回帰しました。
分散の本質は銘柄の数ではなく、リスク源泉を分けること。全世界株を通じて数千社に投資しているなら、個別株を20銘柄持つよりもよほど分散されています。
また、分散は「時間軸」にもあります。毎月定額を積み立てることで、買値を平均化できるドルコスト平均法。これも立派な分散投資です。私は給料日に自動で引き落とされるよう設定し、“考えずに続ける仕組み”を作りました。
「低コスト」を軽視しない
長期投資では、信託報酬の差が最終リターンを大きく左右します。
たとえば1,000万円を年5%で20年間運用した場合、信託報酬が1%なら約2,190万円、0.1%なら約2,600万円。たった0.9%のコスト差でも、最終的に400万円以上の差になります。長期投資では「低コスト」こそが最大の武器です。
私は「eMAXIS Slim」「SBI・Vシリーズ」など、業界最低水準のファンドを中心に選んでいます。0.1%以下の運用コストを探すのが“日課”のようになりました。
もう一つの「低コスト」は、売買回数を減らすこと。2021年頃まではSNSで話題の銘柄につい手を出してしまい、手数料と税金で利益を削っていました。今では、1年を通じて売却はほぼゼロ。売らないことで課税を先送りし、複利を最大限に活かしています。
投資の世界では「何を買うか」よりも、「何をしないか」が大切だと痛感しています。
平社員でも「資産維持」は可能
7,000万円という金額は決して“勝ち組”ではありません。むしろ、家計管理と投資の両立でようやく到達できたラインです。
現在は教育費がピークを迎え、つみたて額も月13,000円に減らしました(オルカン1万円+S&P500 3,000円)。それでも続けているのは、「止めると再開が難しい」ことを知っているからです。
積立を続ける限り、経済成長と時間が味方をしてくれる。たとえ1万円でも、10年後・20年後には確実に意味を持ちます。
また、我が家は賃貸暮らしで住宅ローンがないため、金利上昇の影響を受けにくい点も資産維持に寄与しています。持ち家の修繕や固定資産税を考えると、賃貸の自由度は50代以降にこそ価値があると感じます。
資産を守るとは「減らさない仕組み」を持つこと。高配当株や不動産などにも興味はありますが、分散目的を超えた“欲張り投資”は避けています。
2025年の物価高・円安をどう見るか
近年は円安・インフレが続き、「日本円の価値が下がっている」と言われます。確かに実感として、外食も電気代も上がりました。
ただ、だからといって慌てて外貨やゴールドに資金を移すのは危険です。私は円建て資産を維持しつつ、投資信託を通じて自然に海外資産を持つ形を選びました。
オルカンやS&P500に投資していれば、為替分散も自動的に行われます。つまり、特別な対策を取らずとも、すでにインフレ耐性があるのです。
一方、現金比率も一定程度は確保しています。生活防衛資金として1,000万円程度を普通預金に置き、残りを運用に回す。株価が下がっても取り崩さずに済む“心の余裕”があるからこそ、暴落時にも冷静でいられるのだと思います。
まとめ:地味でも続ける人が勝つ
「長期・分散・低コスト」は、一見すると退屈で、派手さのない戦略です。
しかしこの地味な積み上げこそ、50代の私が安定して資産を維持できている最大の理由です。
株価の上げ下げよりも、「習慣化できる仕組み」を作ること。積立額を自動化し、余計な判断をしない。それだけで投資は成功に近づきます。
年収や役職に関係なく、家計のバランスを整え、続ける仕組みを作れば、資産形成は十分可能です。
「もう遅い」と感じている50代の方こそ、今から始めても遅くありません。少額でもいい、焦らず、欲張らず、自分のペースで積み上げていきましょう。
老後の安心は、一夜にして得られるものではなく、日々の地味な選択の積み重ねでしか生まれません。私はそのことを、20年かけてようやく実感しています。
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
















