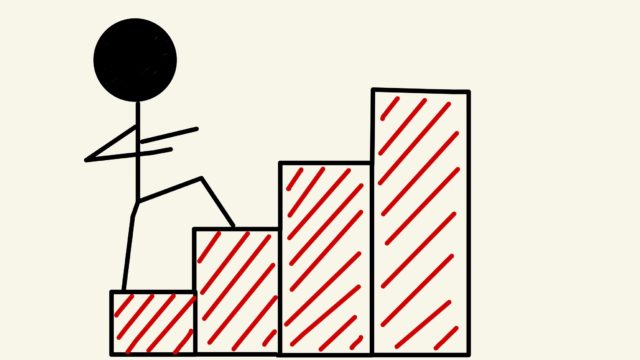■ 「靴磨きの少年の話」とは何か
投資の世界では、「靴磨きの少年(Shoeshine Boy)の話」という有名な逸話がある。
1929年のアメリカ、世界大恐慌の直前に、政治家ジョセフ・ケネディ(JFKの父)がウォール街で靴を磨いてもらっていたときのこと。
少年が彼にこう話しかけたという。
「今は〇〇という株がいいらしいですよ。僕も少し買おうかと思ってるんです」
その瞬間、ケネディはこう感じたそうだ。
「靴磨きの少年までが株の話をしている──これは市場が過熱している証拠だ」
そして彼はすぐに株をすべて売却した。
直後に1929年の大暴落が起こり、ケネディは難を逃れた──というのがこの話の筋書きだ。
この逸話は長年にわたって、投資の“警句”として語り継がれてきた。
つまり、「素人が株を買い始めたとき、相場は天井だ」という戒めとして。
一見、賢明な投資家の洞察のように思える。
だが私は、この話がどうしても好きになれない。
その理由は、この物語に人を見下す視線と職業差別的な価値観が透けているからだ。
■ 「靴磨き=無知な大衆」という偏見
靴磨きの少年は、ただ生活のために働きながら、世の中の景気や株式市場に興味を持っただけかもしれない。
それを「相場の終わりの象徴」として使うこと自体が、まるで労働者階層の知的関心を嘲笑する構図に見える。
「靴磨きが株を語るなんて、おかしい」
そう考える時点で、すでに職業で人を区別する発想がある。
知識を持つこと、学ぶこと、経済に参加することを“身分の低い者”がしてはいけないとするような意識が潜んでいる。
これが、この話に対して私が感じる強烈な違和感だ。
■ 情報格差が崩壊した現代にこの話は通用しない
1920〜30年代のウォール街では、情報はごく一部の特権層にしか届かなかった。
新聞も限られ、取引の多くは“知る人ぞ知る”世界で行われていた。
だからこそ、ケネディは「靴磨きの少年が株を語る=情報が大衆にまで漏れた異常事態」と感じたのだ。
だが、2025年の今は違う。
SNS、ネット証券、企業IR、金融庁の監督など、情報はほぼリアルタイムで共有される。
個人投資家も、プロと同じデータを見て判断できる。
情報の非対称性は、歴史的に見て最も小さい時代にある。
それでも、いまだに「靴磨きの少年の話」を得意げに語る投資家がいる。
彼らは「大衆が投資を始めたら危ない」と言うが、実際には大衆がようやく正しい知識を得て参加できるようになっただけのこと。
この変化を理解できない方が、よほど無知である。
■ 金融リテラシーが広がることは“健全化”である
いまや新NISAやiDeCoを通じて、誰もが資産形成に関われるようになった。
若い会社員が積立投資を始め、主婦がインデックスファンドで老後資金を作り、高校生までも金融教育を受けている。
これは社会の成熟と金融の民主化の証である。
それを「素人の熱狂」と決めつけるのは、時代錯誤だ。
むしろ、金融リテラシーが社会全体に広がることで、投資は“博打”ではなく“生活設計の一部”として定着してきた。
「靴磨きの少年が株を語る時代」は、もう“危険信号”ではない。
それは、社会がようやく成熟したサインなのだ。
■ 職業や階層で人を測る時代ではない
現代では、靴磨きの少年がいたとしても、彼はスマホで経済ニュースを読み、YouTubeで金融知識を学び、つみたてNISAを活用しているかもしれない。
それを笑うことに何の意味があるだろうか。
本当に知識ある投資家なら、他人を軽んじない。
市場の動向を「大衆が買っているから危険だ」と一括りにせず、
ファンダメンタルやバリュエーションをもとに判断する。
他人の行動を“警句”に変えるのではなく、自分の判断軸を磨くことこそ投資家の成熟だ。
■ 投資家が持つべき倫理観とは
投資には知識だけでなく、倫理が求められる。
「自分は分かっている」「あいつらは愚かだ」と他人を見下す発想は、
市場そのものへの謙虚さを失わせる。
真に成熟した投資家は、他人の投資行動を笑わない。
靴磨きの少年も、サラリーマンも、主婦も、学生も、
皆それぞれの立場で未来に備えようとしている。
それを笑う者こそ、精神的に貧しい。
■ “群衆”を恐れるのではなく、“無理解”を恐れよ
「靴磨きの少年が株を語ったら天井だ」と言う人は、
本当は“群衆心理”ではなく、“自分の無理解”を恐れるべきだ。
現代では、AI取引や指数連動資金など、相場を動かす主役は機関投資家やアルゴリズムである。
個人投資家が少し増えた程度で市場が崩れることはない。
それでも「大衆が投資を始めたら危ない」と語る人は、
ただの感情論であり、根拠なき優越意識にすぎない。
■ 結論:無知なのは“靴磨きの少年”ではなく、時代を見ない投資家だ
時代は変わった。
情報は開かれ、制度は整備され、教育も広がった。
それでも「靴磨きの少年の話」を振りかざす人がいるなら、
それはもう“知識人”ではなく、“過去の亡霊”にすぎない。
もし今、街角で靴を磨く少年がいたら、
きっとスマホで積立設定を済ませ、
「将来は自分の店を持ちたい」と語っているだろう。
そんな彼を笑う者がいるなら、
その人こそが、いちばん時代遅れで、いちばん無知だ。
投資は誰のものでもない。
立場も職業も関係ない。
必要なのは、“他人を見下さない知性”と“自分の頭で考える力”だけだ。
靴磨きの少年を笑う投資家こそ、真に学ぶべき相手なのかもしれない。
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。