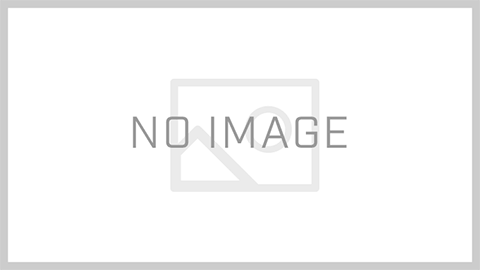新NISA利用者の平均投資額と運用益は?データで見る“投資格差”

2024年に始まった新NISAは、多くの個人投資家にとって「資産形成の柱」となりつつあります。しかし、実際にどれくらいの金額を投資し、どの程度の運用益を得ているのか——。この「投資格差」の実態を知ることで、自分の立ち位置を冷静に見直すきっかけにもなります。今回は、最新データをもとにその現状を整理します。
平均投資額はおよそ160万円、中央値は60万円前後
金融庁の公表資料や主要証券会社の調査によると、新NISA利用者の平均投資額は約160万円前後。ただしこの数値はあくまで平均であり、実際の多くは100万円未満の範囲に集中しています。
興味深いのは中央値が60万円前後にとどまっている点です。つまり、ごく一部の高額投資層が平均値を押し上げている構図で、投資格差の広がりを示しています。
例えば、筆者のまわりでも「年間120万円満額で積み立てる人」と「月1万円だけの慎重派」に二極化しています。新NISAは制度上の上限が広がったものの、実際には家計余力や投資経験によって行動が分かれる現実があります。
さらに注目すべきは、年齢層による傾向の違いです。40〜60代の利用者は平均投資額が高い一方、20〜30代ではまだ貯蓄段階にあり、少額から始めるケースが大半。資金余力がある世代ほど初期投資が大きくなり、複利効果でも差が開きやすいのです。これがいわゆる「世代間投資格差」を生み出す要因にもなっています。
運用益の実態:多くの人がプラスだが、差が大きい
日本証券業協会の2025年上期調査では、新NISA利用者の約8割が評価益を得ていると回答しています。特に2024年〜2025年にかけて米国株式市場が堅調だったことも追い風となり、S&P500やオルカン(全世界株式)に投資している層は軒並みプラス。
一方で、個別株やテーマ型ETFに偏った投資をした層では、マイナスのままの人も約2割に達しています。
実際、平均運用益率は+12〜15%程度と報告されていますが、中央値では+6〜8%に落ち着くケースが多いようです。つみたてNISA時代よりも金額が大きくなった分、損益の振れ幅も拡大しました。
ここで注意したいのは、「投資格差=悪いこと」ではないという点です。投資はもともとリスクとリターンが表裏一体。むしろ、各人が異なる目的やリスク許容度に合わせて行動している結果として差が生まれるのは自然なことです。問題なのは、その差を“焦り”や“比較”の材料にしてしまうことです。
“投資格差”を生む3つの要因
1つ目は「投資開始時期の差」。2020年以前から積み立てを続けてきた層は、コロナ後の上昇相場で大きく資産を増やしました。新NISAから始めた層とは、わずか数年でもリターンに数十%の差が生まれています。
2つ目は「商品選びの差」。インデックス投資で市場平均を取るか、個別株で上振れを狙うか。この選択が中長期の成績を大きく左右します。特に短期売買を繰り返すタイプほど、手数料やタイミングミスで成果が伸び悩む傾向があります。
3つ目は「継続力の差」。積み立てを途中でやめる人と、相場に左右されず継続できた人では、10年後に大きな差がつきます。結局、最も強いのは「何もしないで続けられる人」です。
新NISAは「満額投資」だけが正解ではない
SNSでは「満額投資してこそ意味がある」という声も見かけますが、現実には無理のないペースで続けることの方が重要です。筆者自身、2024年から積立額を月33,333円から13,000円に減額しました。家計支出が増えた50代として、“継続できる額”を優先しています。
資産形成の目的は「他人より多く儲けること」ではなく、「将来の安心をつくること」。その意味では、平均額より少なくても、時間を味方につけて続ける姿勢こそが最大のリターンにつながります。
特に50代以降は「守りながら増やす」発想が欠かせません。余裕資金で分散投資を行い、短期の値動きで慌てず、定期的に資産配分を見直す——。この“地味な習慣”が最終的に大きな差を生むのです。
投資格差を「焦り」ではなく「学び」に変える
新NISAの口座数は2025年6月時点で約3,200万口座に達し、すでに国民の4人に1人が利用する規模です。これほど多様な層が参加する投資制度で、成果の差が出るのは自然なこと。
大切なのは「自分の目的とリスク許容度に合った投資スタイル」を明確にすることです。
筆者も20年近く投資を続けてきましたが、途中でブレて損をした経験が何度もあります。最終的にたどり着いたのは、長期・分散・低コストという原点でした。焦って動くほど、得られるリターンは小さくなる——これは多くの個人投資家が実感しているはずです。
まとめ:平均より“継続力”が最強の武器
新NISAのデータを見ると、投資格差は確かに存在します。しかし、それは努力や知識の差というより、「続けたかどうか」の違いです。
月1万円でも20年続ければ、積立総額は240万円。仮に年5%で運用できれば、約400万円に増えます。これが「地味でも再現可能な成果」です。
投資はマラソン。途中で休んでもいい、ペースを落としてもいい。やめなければ、ちゃんとゴールに近づきます。
平均額や他人の利益に惑わされず、自分の歩幅で続ける——それが、投資格差を超える唯一の道だと感じています。
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。