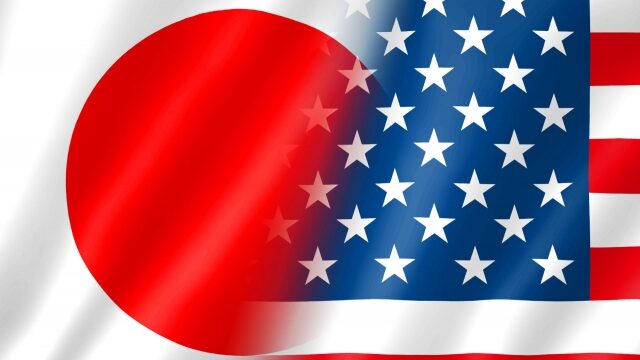投資は元手が9割|まず100万円を作り、新NISAで増やす

投資の成果は「才能」よりも「元手」で大きく変わります。同じ5%で運用しても、投資額が10倍違えば得られる金額も10倍。だからこそ、まずは元手を作り、次に仕組みで増やす。
50代の私もこの順番で積み上げてきました。この記事では、最初の100万円を作る現実的な方法と、新NISAでコツコツ増やす道筋をまとめます。
なぜ「投資額」が結果を左右するのか
株式市場では、お金持ちも庶民も“同じ商品に投資すれば同じ利回り”です。違いは投入できる金額だけ。複利が働くほど差は雪だるま式に開きます。
投資の議論は「どの商品が強いか」に偏りがちですが、実は“いくら入れられるか”の設計がリターンの大半を決めます。
数字で実感:100万円と1,000万円、年5%での差
・1年後の運用益:100万円→+5万円、1,000万円→+50万円
・10年後の元利合計:100万円→約162.9万円(利益約62.9万円)/1,000万円→約1,628.9万円(利益約628.9万円)
・20年後の元利合計:100万円→約265.3万円(利益約165.3万円)/1,000万円→約2,653.3万円(利益約1,653.0万円)
同じ“5%”でも、元手の差がそのまま「お金の差」になります。だから、商品選びより先に“入金力の確保”を最優先に。
まずは元手を作る——貯金ゼロからの現実策
借金で投資はおすすめしません。最初にやるべきは「貯める仕組み化」です。ここで生活を締めすぎると続きません。続く最低限の工夫だけに絞ります。
先取り貯蓄を“仕組み”にする
給与日に別口座へ自動振替。キャッシュカードは作らない。毎月の積立定期にして簡単に引き出せないようにする——この原始的な方法がいちばん効きます。
最初の目標は“貯金100万円”。生活防衛資金の土台ができると投資のメンタルが安定します。詳しい節約のコツは、手取り20万円台でも貯められる!50代サラリーマンのリアル節約術にまとめています。

クレジットカードは順番を守る
カード払いは本来お得ですが、管理が苦手ならデビットやプリペイドに一時的に切り替え、リボ・分割は封印。貯金100万円を達成してから通常運用へ戻すのが無難です。借金があるなら“完済→現金主義→再開”の順番で。
家計の見直しは“固定費から”
通信(格安プラン化)、保険(過剰保障の整理)、住居(更新時に家賃交渉や引っ越し検討)——ここで月1〜3万円が空けば、貯蓄と新NISAの両方に回せます。
新NISAで“自動で増やす”
2024年から新NISAがスタートし、非課税期間は恒久化、生涯投資枠は1,800万円(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円、年間最大360万円)になりました。
インデックス投資の積み立てに最適です。私は家計の事情で2024年から毎月1.3万円(オルカン1万円+S&P500 3,000円)に減額しましたが、続けることを最優先にしています。設定したら“見ない・触らない・止めない”。

何に積み立てる?
長期・分散・低コストの原則に合う商品(全世界株や米国株のインデックス)が第一候補。配当再投資で効率よく増やす。

ミニ計算:積立の力を数字で見る
・毎月1.3万円を年5%で20年積み立て→約534万円(元本312万円)
・毎月1.3万円を年5%で30年積み立て→約1,082万円(元本468万円)
・毎月3万円を年5%で20年積み立て→約1,233万円(元本720万円)
・毎月3万円を年5%で30年積み立て→約2,497万円(元本1,080万円)
“少額でも止めない”ことが、将来の選択肢を増やします。
今日からできる3ステップ
1)“先取り貯蓄+新NISA”の自動化(給与日に同時発車)
2)ボーナス・臨時収入の一定割合(例:30%)は無条件で投資口座へ移すルール化
3)年1回の点検だけ実施(積立額の増額可否、商品コストの再確認)——それ以外は相場ニュースを遮断
目標の刻み方:100万円→300万円→1,000万円
1)固定費の見直し(通信・保険・住居)で月1〜3万円を捻出
2)“先取り貯蓄+新NISA積立”を並行運用
3)年1回だけ増額余地を点検(昇給・ボーナス時に+3,000円など)
4)住まいは“流動性と総コスト”で判断。
よくある落とし穴と回避策
・借金でレバレッジ投資:景気後退時に一発退場のリスク。余剰資金でのみ投資
・“毎月分配型”など高コスト商品:手数料が複利の敵。低コストインデックスが基本
・相場ニュースに振り回される:売買回転は税・手数料でリターンを削る。積立継続に集中
・保険の入りすぎ:保障は最小限、投資と混ぜない(貯蓄型の高コストに注意)
・住宅ローンの過大化:返済負担率の目安を超えない。住まいは“身の丈+流動性”で
Q&A:先に投資?それとも貯金?
私は“貯金100万円までは貯金優先、以後は貯金と新NISAを並行”派です。理由は、急な出費で投資を取り崩すと、心理的ダメージが大きいから。
防衛資金があれば暴落時にも積立を続けやすくなります。暴落が怖いなら、積立日は固定、ニュースは最小限、年1回だけ進捗確認——これで十分です。
私の失敗から学んだこと(50代の実感)
若いころは「上がりそう」に飛びつき、下がると怖くて売っていました。結局、資産は増えませんでした。転機は“先取りで貯める→仕組みで積み立てる→増やすのは時間に任せる”に切り替えたこと。
毎月の入金が細くても、止めなければ資産カーブは右肩に整っていきます。家族の学費や介護費などライフイベントが重なる時期でも、積立を細くして継続する姿勢が一番の近道でした。
まとめ
投資のパフォーマンスは同じでも、結果は“元手”で大きく変わります。だからこそ、最初の100万円を仕組みで作り、新NISAで淡々と増やす。
これが再現性の高い道筋です。節約や住まい、保険の見直しといった土台づくりも同時に進めてください。今日始めた1万円が、10年後・20年後の選択肢を確実に広げます。
リスク管理の基礎:売らないための工夫
・生活防衛資金は最低6か月分を現金で確保(心の安定が最強のリスクヘッジ)
・証券口座の自動引落を設定し、“手動の判断”を減らす
・ポートフォリオはシンプルに:全世界株インデックス80%+現金20%など、自分が続けられる配分に固定
・暴落時の行動指針を事前に決める:積立は淡々と継続、必要ならリバランス、ニュースの見過ぎ禁止
小さく始めて、大きく育てる
始めは毎月1万円でもOK。重要なのは“やめない”ことです。収入が上がったら+3,000円、支出を1つ削れたら+2,000円……この積み増しが未来の差になります。
市場の当たり外れを狙うより、入金力を少しずつ底上げする方が、はるかに再現性が高い。
本記事の活用法(行動チェックリスト)
・給与日に“先取り貯蓄+新NISA引落”のW自動化を設定したか
・固定費の見直しで今月捻出できる金額はいくらか(目安:1〜3万円)
・貯金100万円までのロードマップ(何か月で到達するか)を紙に書いたか
・積立商品は低コストか、信託報酬は年0.5%未満かを確認したか
・相場ニュースに接する時間を1日5分以内に制限できているか
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。