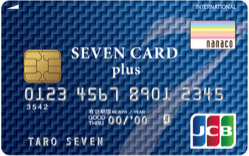【要注意】リボ払いは最終手段!その前に考えるべき3つの選択肢(2025年版)
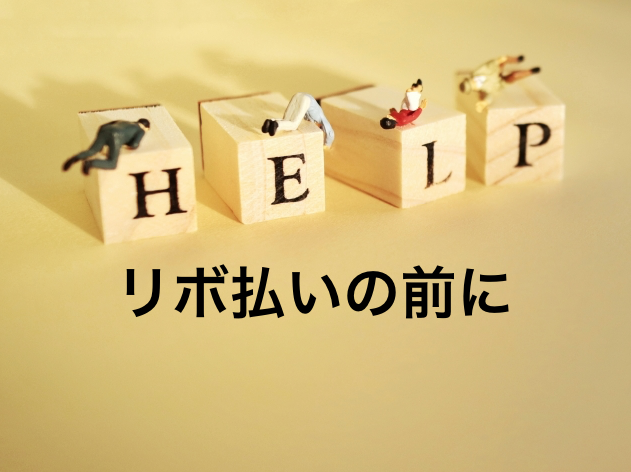
急な収入減や支出の増加で、クレジットカードの支払いに困ったことはありませんか?
特に近年は物価高や不安定な雇用情勢の影響で、家計のバランスを崩してしまう人も少なくありません。そんな時、「とりあえずリボ払いにすれば…」と考えてしまいがちですが、ちょっと待ってください。
リボ払いはあくまで“最後の手段”です。
この記事では、リボ払いを使う前に検討してほしい3つの選択肢と、リボ払いのリスクについて解説します。
まず検討すべき3つの選択肢
本当に困ったときには、以下の順番で対応を検討してみてください。
① 生活福祉資金貸付制度(無利子・低利子の公的支援)
厚生労働省の支援制度で、自治体の社会福祉協議会が窓口です。以下の2つの貸付が利用できます。
-
緊急小口資金:収入減に対応するための一時的な貸付(休業・減収が理由でも対象に)
-
総合支援資金:失業や生活困窮者向けの生活費貸付
いずれも無利子または低利子で、返済の猶予期間があるケースもあります。市区町村の社会福祉協議会に問い合わせてみましょう。
② 家族や知人に相談する
公的制度が使えない場合、身近な人に助けを求めるのも現実的な手段です。
もちろん、「頼みにくい」「気まずい」という心理的なハードルはあるでしょう。しかし、高金利のリボ払いに比べれば、精神的・金銭的ダメージは小さく済む可能性があります。
※ただし、関係が悪化する可能性がある相手には借りないようにしましょう。信頼できる人に限定するのがポイントです。
③ 勤労者生活資金融資制度(ろうきんの低金利融資)
各自治体がろうきん(労働金庫)と連携して提供している、労働者向けの低金利融資制度です。
【例】横浜市の場合:
-
資金用途:教育費、医療費、介護、生活費、耐久消費財など
-
金利:年1.4~2.0%前後(用途により変動)
-
保証料:年0.7〜1.2%
こちらも育児や介護の休業中でも相談できるケースがあります。自治体ごとに内容が異なるため、お住まいの市区町村のろうきんに相談を。
リボ払いとは?仕組みと落とし穴
リボ払いとは、利用金額にかかわらず毎月の支払い額を一定にできる支払い方法です。
例:10万円使っても、毎月の返済を「1万円」と設定できる。
一見便利ですが、実際には年率15〜18%前後の手数料(利息)がかかり、支払い期間が長くなるほど、元本がなかなか減りません。
さらに、支払いが遅れると遅延損害金(年20%)が上乗せされ、返済総額はどんどん膨らみます。これはまさに「借金を先延ばしにする仕組み」であり、安易に使うべきではありません。
リボ払いが“最終手段”である理由
それでもどうしても支払いができず、信用情報(クレジットヒストリー)に傷がつく恐れがある場合のみ、最後の手段として検討する余地があります。
信用情報に延滞記録がつくと:
-
クレジットカードの更新が拒否される
-
住宅ローンや自動車ローンの審査が通らない
-
スマホの分割払いができなくなる
など、日常生活に支障が出ることも。そうした事態を避けるため、「信用を守る」ための選択肢として、やむを得ずリボ払いを使うという考え方もあります。
まとめ:まずは公的支援や身近な人を頼る勇気を
リボ払いは「便利そう」に見える一方で、その仕組みをよく理解していないと借金地獄の入り口になりかねません。
支払いに困ったら、まずは以下の順で対応を検討してください。
-
✅ 生活福祉資金貸付制度(市区町村の社協)
-
✅ 家族や知人への相談
-
✅ ろうきんの低金利融資制度
-
✅ 最後の手段としてのリボ払い
冷静に情報を集め、将来の自分を守る選択をしましょう。特に信用情報は、長期的にあなたの人生に大きな影響を与える資産です。
推奨タイトル案(SEO対策向け):
-
【2025年版】リボ払いは危険?絶対に知っておきたい代替手段3選
-
【リボ払いのリスク】使う前に確認すべき公的制度と選択肢
-
リボ払いは最後の砦!損しないために考えるべき3つの対応策
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。