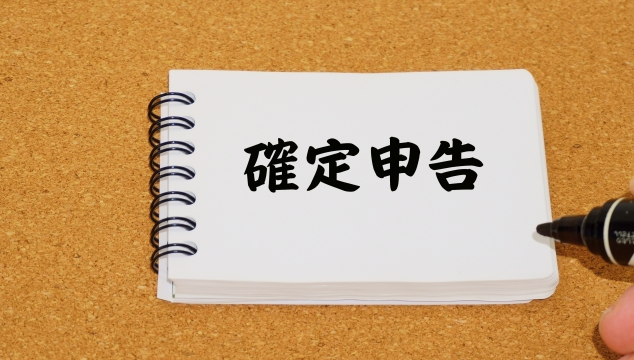50代になると、「もう十分じゃないか」とふと感じる瞬間がある。
20代や30代のように時間が無限にあるわけではなく、老後が現実味を帯びてくる。
株価が少し下がるだけで、心がざわつく。
私も同じだった。
積立を続ける気力が薄れ、「もうやめてもいいのでは」と思ったことが何度もある。
しかし、私の周りには“その後の結果が大きく分かれた人たち”がいる。
投資をやめた人と、続けた人。
どちらが正解だったかは10年後にしかわからないが、その「分かれ道」には明確な傾向がある。
今回は、私自身の経験も交えて整理してみたい。
投資をやめた人に共通する3つの理由
1. 損失が怖くなった
投資をやめた人の多くは、相場の下落をきっかけに手を引いた。
「含み損が出ると気持ちが持たない」「一度リセットしたい」という声をよく聞く。
50代になると“リスクを取れる時間が減った”と感じるため、損失への耐性が下がるのは自然だ。
だが、そこで売却してしまうと“安く売って高く買い戻す”という最悪のパターンになる。
時間がないからこそ、動かない勇気が求められる。
2. 家計が苦しくなった
子どもの教育費、親の介護、そして自分の老後。
50代は出費のピークが重なる時期だ。
「まずは現金を確保しないと」と考え、積立を止める人は少なくない。
私も一時期、つみたてNISAの月33,333円を13,000円に減額した。
(オルカンに1万円、S&P500に3,000円ずつ)
生活の安定を優先するのは間違いではない。
ただ、完全に止めてしまうと再開のきっかけを失う。
“減らしても続ける”という選択肢を残すことが、のちの回復力につながる。
3. 目的を見失った
投資を続ける理由が「儲けたい」だけだと、相場が下がった瞬間に心が折れる。
一方、「老後の安心」「家族の生活を守る」といった目的を明確にしている人は強い。
数字ではなく、“生活の支え”として投資を位置づけている。
やめた人の多くは、スタート時の目的を思い出せなくなっていた。
続けた人がやっていた3つのこと
1. 生活と投資を切り分けていた
続けた人に共通しているのは、投資と生活を混同しないことだ。
投資は「余剰資金」、生活費は「日常資金」。
この線引きが明確な人は、相場が荒れても動揺しない。
積立設定を自動化し、余ったお金で家族と外食を楽しむ。
そんな“生活と投資の共存”が続ける力になる。
2. 見ない勇気を持っていた
続けた人ほど、日々の値動きを見ない。
スマホで株価を確認する習慣を捨て、毎月の積立をただ淡々と続ける。
暴落しても、「口座を開かない期間」を意図的に作る。
これは意外と効果がある。
ニュースで“株価暴落”と流れても、心を動かさない訓練になる。
見ないことも立派なリスク管理だ。
3. “心のシミュレーション”をしていた
投資を続けた人は、「もし暴落したらどうするか」を事前に決めている。
「積立は止めない」「売らない」「買い増す」など、マイルールを明文化している。
この“心の予行演習”があるだけで、実際の暴落時に慌てない。
投資の成功とは、結果ではなく「感情を制御できた回数」の積み重ねだと思う。
私が「続ける」と決めた理由
私自身、投資歴は18年ほどだが、最初の10年は迷いの連続だった。
リーマンショックで半分になった資産を見て、何度もやめようと思った。
だが、不思議なことに“続けた年ほど資産は増えていた”。
つまり、継続こそが最大の武器だったのだ。
50代になり、積立を減額することはあっても、ゼロにはしない。
理由は単純で、積立を止めると「自分の成長も止まる」気がするからだ。
少額でも続けることで、「今も資産を育てている」という感覚を保てる。
これは数字以上に大きい。
やめた人・続けた人の差が出るのは10年後
50代で投資をやめた人は、「守りたい」気持ちが勝った人だ。
一方で続けた人は、「育てたい」気持ちを捨てなかった人。
その差が本格的に現れるのは60代以降だ。
例えば、毎月1万円を10年積み立てるだけで、利回り5%なら約155万円になる。
止めた人はそこで終わり。
続けた人は、それを“次の10年”に乗せる。
複利の効果で資産が2倍近くになるのは、その後なのだ。
だからこそ、「もういいか」と思った時が、本当の勝負。
やめるか、続けるか──この小さな決断が老後の安心を分ける。
まとめ:やめる勇気より、続ける覚悟を
投資をやめた人は「怖くなった人」、続けた人は「信じた人」。
ただし信じるべきは“市場”ではなく“自分のルール”だ。
毎月の積立を少しでも続けることで、未来の自分に安心をプレゼントできる。
50代の投資とは、派手な勝負ではなく、静かな継続力の勝負。
やめる勇気より、続ける覚悟を持つこと。
それが、私たちの“逃げ切り戦略”の第一歩だと思う。
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。