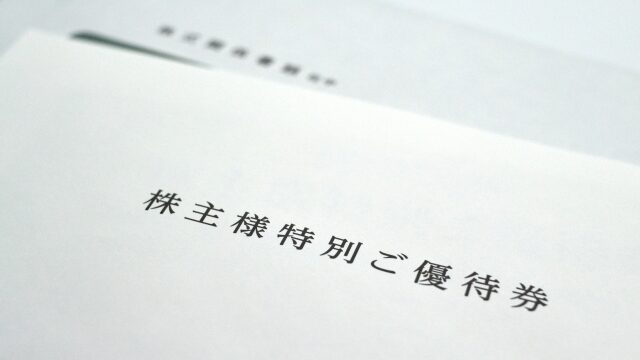私はこれまで、税金のことをあまり深く考えずに過ごしてきました。毎月の給料から自動的に天引きされ、年末調整で会社が手続きをしてくれる――多くのサラリーマンにとって、税金は「任せておけば大丈夫なもの」です。
しかし、これからの時代はそうもいかなくなります。少子高齢化で社会保障費が増え、財政赤字を埋めるために増税が続く。そんな中で「自分がいくら税金を負担しているのか」を知っておくことが、老後資産を守る第一歩になると感じています。
税金を“自動引き落とし”に任せすぎていないか
私たちサラリーマンは、所得税・住民税・社会保険料などを毎月給与天引きされています。会社が代わりに納付してくれるため、税金を意識する機会は少ないでしょう。けれども、実際に源泉徴収票を見て「1年間でいくら引かれているのか」を確認したことがある人は、意外と少ないのではないでしょうか。
私の場合、初めてしっかり見たときは正直驚きました。額面から社会保険料と税金を引いたあとの手取りの少なさに、現実を突きつけられたのです。これを“他人任せ”にしていると、家計の改善も、政治への関心も生まれません。
2025年の税制改正と「定額減税」の実態
2025年(令和7年)現在、話題になっているのが「定額減税」です。
政府は物価高への負担緩和策として、所得税で1人あたり3万円、住民税で1万円、合計4万円を減税する制度を導入しました。給与所得者の場合、会社が年末調整や6月支給分の給与で自動的に反映する形になっています。
ただし、注意したいのは「全員が4万円減税されるわけではない」という点です。対象は年収2,000万円以下の人に限られ、課税所得が低い人は所得税がそもそも少ないため、恩恵を感じにくい場合もあります。また、住民税の減税分が翌年に反映されるなど、時期のズレもあります。
つまり、「減税された」というよりも「一時的な調整」に近いのです。今後も社会保障費の増大により、トータルでは税・保険料の負担増が続くことはほぼ確実です。
サラリーマンでも使える控除を活かす
とはいえ、私たちにも節税の余地はあります。
会社員が利用できる主な控除には次のようなものがあります。
-
生命保険料控除(最大12万円)
-
地震保険料控除
-
医療費控除(10万円超の医療費が対象)
-
配偶者控除・扶養控除
-
小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)
-
ふるさと納税(寄附金控除)
特にiDeCoは「節税+老後資金づくり」が両立できる有効な制度です。掛金が全額所得控除になるため、毎月1万円でも積み立てていけば所得税・住民税を年間数千円~1万円以上減らすことも可能です。
また、医療費控除やふるさと納税も電子申告(e-Tax)を使えば手続きが簡単です。私も最近はスマホでマイナンバーカードを読み取って申告しています。紙の書類をそろえる手間が減り、確定申告のハードルはずいぶん下がりました。
増税とインフレのダブルパンチに備える
ここ数年、給料が多少上がっても実感が乏しいと感じませんか。
理由は簡単で、物価と税・社会保険料が同時に上がっているからです。電気代・食料品・ガソリンなどの生活コストが上がる中で、可処分所得(自由に使えるお金)はむしろ減っている家庭が多いと思います。
サラリーマンにとって税金の増加は避けられません。だからこそ、税制を知り、できるだけ「控除」「非課税枠」を活用することが重要です。
節税とは、裏技でも抜け道でもなく「制度を正しく使うこと」。それだけで年間数万円単位の差が生まれます。
投資と税金の関係を理解しておく
近年の制度改正で、投資の税制優遇も進んでいます。
2024年から始まった「新NISA」は、売却益・配当が非課税になる非常に有利な仕組みです。私はつみたて投資枠でオルカン(全世界株)とS&P500を少額ずつ積み立てています。
非課税枠を活用することで、20%の税金を払わずに済む。これは立派な「節税」です。
一方で、NISA外の口座で売却益が出た場合には、特定口座(源泉徴収あり)でも自動的に税金が引かれる点を理解しておきましょう。投資が増えると確定申告が必要になる場合もありますが、税金の仕組みを理解していれば難しくありません。
結局のところ、税金は「知っている人が得をし、知らない人が損をする」仕組みになっているのです。
まとめ:1年に1回、自分の税金を“見える化”する習慣を
サラリーマンはつい「会社がやってくれる」と思いがちです。
しかし、1年に1回くらいは源泉徴収票を開き、自分がどれだけ税金を払っているのかを確認してみましょう。控除を見直すことで、思わぬ節税につながることもあります。
私も毎年、確定申告の時期には「今年もこれだけ社会に貢献した」と思いながら、数字を見ています。そこには家計の現実と、将来へのヒントが隠れています。
税金を知ることは、資産を守ること。これからの時代、サラリーマンほど“税金リテラシー”が問われるのではないでしょうか。
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。