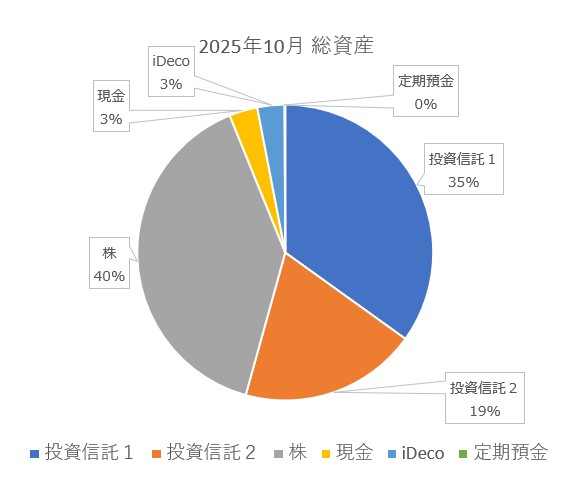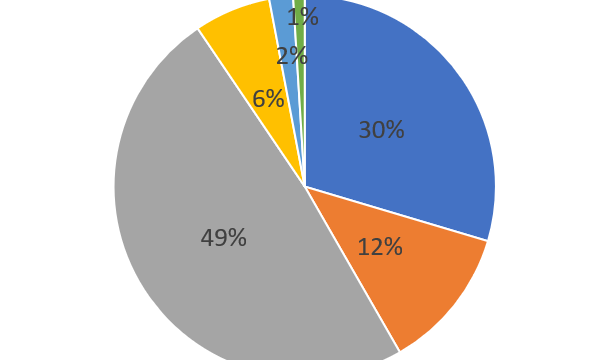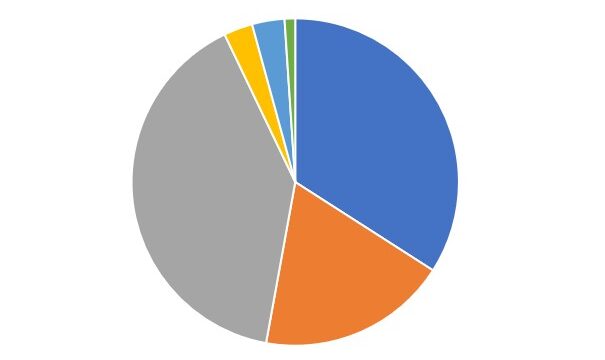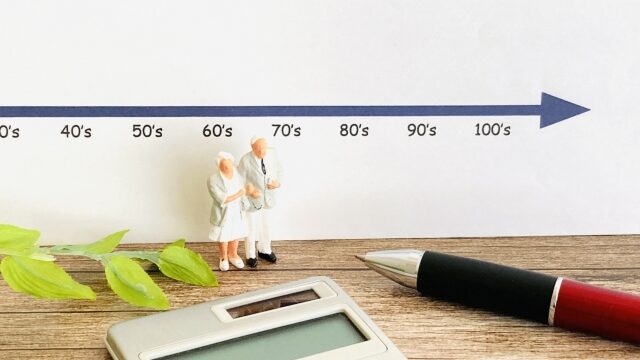【資産8,000万円突破】ETF長期保有で到達した50代サラリーマンの現実
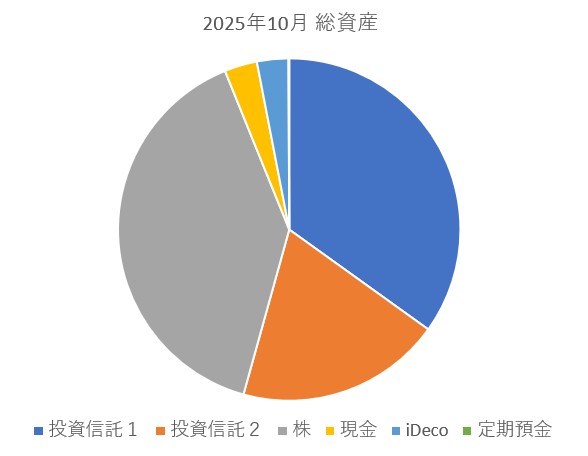
今月も恒例の総資産を公開します。
2025年10月時点で、私の総資産は8,138万1,615円となり、ついに8,000万円を超えました。
長く積み立てを続けてきた身として、この数字を目にしたときはやはりうれしさがこみ上げました。
ただし、これは「瞬間最大風速」にすぎません。
10日の米国株の下落はまだ反映されておらず、14日の連休明けには日本株も下げる可能性が高い。
来週には再び7,000万円台に戻っているかもしれません。
それでも、どんなに一時的であっても「8,000万円を超えた」という事実は大きな節目です。
長期・分散・低コストという地味な積立を、何年も淡々と続けてきた結果だと感じています。
総資産の内訳(2025年10月時点)
| 区分 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 投資信託① | ¥28,411,878 | 34.9% |
| 投資信託② | ¥15,787,513 | 19.4% |
| 株(ETF中心) | ¥32,198,594 | 39.6% |
| 現金 | ¥2,510,195 | 3.1% |
| iDeCo | ¥2,415,425 | 3.0% |
| 定期預金 | ¥58,010 | 0.1% |
| 合計 | ¥81,381,615 | 100.0% |
※「株」区分の約8割はETF(上場投資信託)で構成されています。
国内ETFを通じ、実質的にはインデックス運用を中心としたポートフォリオです。
このように、リスク資産が約97%を占めています。
現金・定期預金は合わせて約260万円ほどしかなく、学費などの支払いによって流動性資金がかなり減りました。
資産全体は大きくなっても、手元資金の減少には正直なところ不安も感じます。
投資は「やめないこと」が最強の武器
私の投資方針は、どんな相場でも積立を止めないことです。
新NISAではオルカン(全世界株)とS&P500を毎月1万3,000円ずつ積み立てています。
以前は月3万3,333円でしたが、教育費の負担が重くなったため減額しました。
それでも「ゼロにはしない」ことを大事にしています。
長期投資の成果は、積立額の多さではなく「続けた年数」に比例します。
ETFやインデックス中心の運用は、個別株のような華やかさはないものの、下落時でも精神的にブレにくいのが利点です。
今回の8,000万円突破も、リスクを取りすぎた結果ではなく、地道な積立と再投資の積み重ねによって達成できたものでした。
家計の現実:教育費と支出の重圧
数字だけを見ると順調そうですが、家計は決して楽ではありません。
10月は子どもの学費の支払いがあり、定期預金をほぼ使い切りました。
さらに来月は子どものメガネの買い替えを予定しており、また数万円単位の支出が発生します。
上の子が高校3年生、下の子が中学2年生。教育費のピーク期です。
同時に、親の介護費も継続的に発生しています。
支出の方向が変わるだけで、50代の家計が「楽になる」ことはありません。
むしろ、資産を減らさずに維持するほうが難しい時期に入ったと感じます。
“増やす”から“守る”への転換期
8,000万円を超えたからといって、積極的にリスクを取りに行く気はありません。
これからは「増やすよりも、守る」フェーズに入ったと考えています。
ETFを保有し続けているのも、売買益を狙うより、
「長期で持ち、配当を再投資しながらじっくり増やす」目的があるからです。
昔買ったETFをいまだに保有しているおかげで、
今では低コストの投資信託と共存する形になっています。
50代の今は、生活リスクを抑えながら現金比率を少しずつ戻していく時期。
年末にかけては一部資産を整理し、教育費や介護資金に備えるつもりです。
特に教育費や介護費用が続く間は、リスク資産を減らして現金比率を少しずつ戻す方針です。
“守りながら続ける”──それが、これからのテーマになりそうです。
まとめ|ETF中心の地味な戦略こそが続けられる強み
今回の8,000万円突破は、数字そのものよりも「ここまで積み上げてきた時間」に意味があります。
ETFやインデックスファンドを中心に、地道に再投資を続けてきたことが結果につながりました。
来月には7,000万円台に戻っているかもしれません。
それでも、私はいつも通り積立を続けます。
資産形成の本質は、“勝ち続ける”ことではなく、“続けられる仕組みを作る”ことだと改めて感じています。
派手さのないETF中心の運用こそ、長期的に安定をもたらす最強の戦略です。
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。