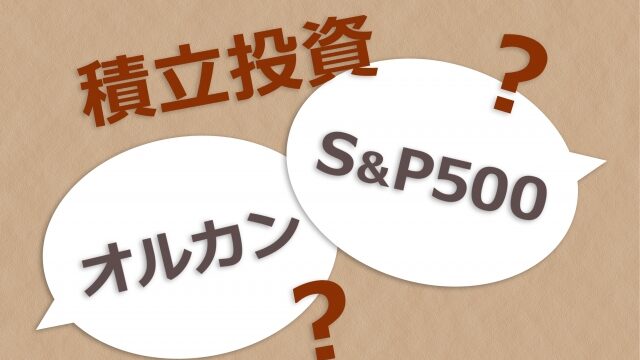経済予測やチャート分析は不要?50代サラリーマンが語る“失敗から学ぶ”長期投資の本質

日々の値動きはノイズに過ぎない
株式市場は毎日動いています。日経平均株価やダウ平均株価が数百円動いた日には、テレビやネットニュースでも大きく取り上げられ、次のような見出しが並びます。
-
「〇〇懸念で大幅安」
-
「米利上げ警戒で売り優勢」
-
「押し目買いの動きが広がる」
-
「警戒感が後退し上昇へ」
一見、もっともらしく感じられますが、多くの場合は“後付けの説明”にすぎません。実際には「材料がないから調整した」「アルゴリズム取引が加速した」など、個人が正確に把握することは困難です。
2025年現在、AIの活用が進み、情報スピードはさらに速くなりました。しかし、長期投資を前提とする個人投資家にとっては、こうした短期的な値動きに右往左往する必要はまったくありません。
日々のニュースを分析しても、長期のパフォーマンスに影響はないのです。時間の無駄になってしまいます。
長期投資の基本:指数と共に歩むメリット
私が実践しているのは、インデックスファンドを使った長期投資です。株式市場全体の成長に乗るスタイルで、世界経済の拡大が続く限り、資産も時間とともに増えていくと考えています。
この投資法のメリットは大きく3つあります。
① 経済活動の成果を着実に享受できる
インデックス投資は、企業の生産活動によって生まれる利益や配当を長期的に享受するスタイルです。保有期間が長くなればなるほど、複利の力が働き、資産が膨らんでいきます。
② 売買の頻度が少なく、コストが抑えられる
頻繁に売買すれば、その都度コストがかかります。手数料や税金も無視できません。長期保有によって、それらを最小限に抑え、資産成長の妨げにならないようにできます。
③ 分散投資によるリスク低減
インデックスファンドは複数の銘柄に分散投資されており、個別企業のリスクを抑えることができます。たとえば、米国S&P500や全世界株式インデックスに投資することで、特定の国や企業に偏らない投資が実現します。
これらのメリットを活かすには、「短期の値動きに左右されないこと」が重要です。ニュースに一喜一憂して投資戦略を変える必要はありません。
チャート分析や経済予測に意味はあるのか?
投資の世界では、チャート分析(テクニカル分析)を使って株価の上下を予測しようとする手法があります。たしかに、一部のプロトレーダーには効果があるかもしれません。
しかし、一般のサラリーマンや家庭を持つ50代の私たちにとって、それを使いこなすには膨大な時間と訓練が必要です。実際、私も過去に試みたことがありますが、利益よりも時間の浪費が目立ちました。
また、経済アナリストの予測も、投資判断の根拠としては不十分です。2025年現在でも、「来年の日経平均は4万円台に?」といった予測が年末になると必ず出てきます。
思い返せば、かつて私も投資雑誌の「プロの予測」に納得して新生銀行の株を購入した経験があります。ところが、数ヶ月で半値以下に下がり、大きな損失を出しました。
これは、プロの予測が必ずしも正しいとは限らないことを身をもって学んだ体験です。
長期投資家が注目すべき「本当に大事な情報」
短期の値動きやアナリストの予測よりも、長期投資家が注目すべきは「国の政策」です。特に以下の情報は、投資環境全体に影響を与えるため、定期的にチェックする価値があります。
-
金融緩和や引き締めの方向性(例:日銀の方針、FRBの動向)
-
政策金利の変更
-
四半期ごとのGDP成長率
-
日本銀行の政策決定会合の内容
-
税制改正の動向(NISAや年金制度なども含む)
-
失業率や雇用統計
-
政府の経済政策全体、特に選挙後の変化
2025年は、世界的なインフレ動向や日本の利上げ観測、エネルギー政策の転換なども注目されています。こうした動きを知っておけば、将来の景気変動に備えるヒントになります。
たとえば「景気が冷え込む兆候がある」と感じたら、生活防衛の観点で支出を控えたり、現金比率を一時的に上げる判断も可能です。
情報は「深掘りして予測に使う」のではなく、「リスクコントロールの材料として活かす」ことが重要です。
まとめ:情報は“使い方”がすべて
最後にお伝えしたいのは、「情報をどう使うか」が大切だということです。
日々の株価の変動や経済ニュースに触れること自体は悪くありません。ただし、それに影響されて投資行動を変えてしまうのは本末転倒です。
長期投資の成功のカギは、「経済成長を信じて市場に居続けること」です。
一方で、経済の基礎知識は備えておくべきです。なぜ円高になると輸出企業の株が下がりやすいのか? なぜ利上げが株価にマイナスの影響を与えるのか? こうした基本的な構造を理解しておくと、情報の取捨選択がしやすくなります。
そして、日々のニュースを「材料としてうまく使う」ことができれば、投資だけでなく日常生活の判断力にも役立つはずです。
👉 FIREは無理。でも50代・平社員の僕が“老後不安”から抜け出そうと思っている話
👉 個人にとっての債権投資と債権価格の計算の仕方。個人投資家にとって債権投資は不要と考える。
👉 【2025年最新版】50代からでも遅くない!新NISAを活用した資産形成術
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。