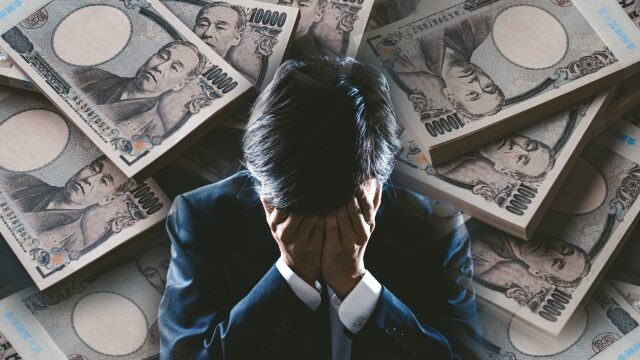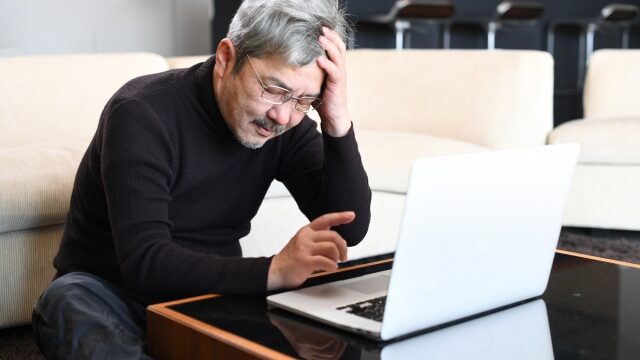家計資産2,239兆円で過去最高!高齢世帯偏在と50代の資産形成

家計金融資産が過去最高を更新
2025年6月末、日本銀行が公表した資金循環統計によると、家計の金融資産残高は2,239兆円となり過去最高を更新しました。前年同期比では約1.0%の増加です。正直、2,000兆円を超えるお金が家計に眠っているという事実は、いつもながら大きなインパクトがあります。私自身も50代となり、日々の投資や貯蓄の行方が気になるところですが、この数字を見ると「日本人はやっぱり貯め込む民族だな」と改めて感じます。
リスク資産が牽引
今回の伸びを支えたのは、株式や投資信託といったリスク資産でした。株式は前年同期比で4.9%増、投資信託は9.0%増と高い伸びを記録しています。背景には、米国株を中心とした株高や円安の影響があります。
私自身も新NISAを通じてS&P500やオルカンに積み立てていますが、円ベースでの評価額は確実に増えています。資産全体が膨らんで見える一方で、円安リスクや市場調整への不安も頭をよぎります。
国債保有の減少と家計の姿勢
一方、国債保有は減少傾向にあります。かつては安全資産の代表とされた日本国債ですが、低金利が続く中で投資妙味が薄れ、家計や金融機関が徐々にリスク資産へシフトしているようです。
私のような50代サラリーマン世代も、昔は「定期預金や国債で十分」と考えていた人が多かったでしょう。しかし、実際には低金利が長引き、預金ではほとんど増えません。だからこそ、新NISAや投資信託を通じた分散投資が広がっているのだと思います。
高齢世帯に資産が偏在している現実
ただし、ここで注意すべきは「誰がその資産を持っているのか」です。資金循環統計そのものは年齢別の内訳を示していませんが、財務省や大和総研の研究によれば、日本の家計金融資産の半分以上は60歳以上の世帯が保有しています。
これは単なる偶然ではなく、長い時間をかけて貯蓄してきた世代が資産を積み上げた結果です。
退職金や年金に加え、現役時代からの投資経験が反映され、統計上も「資産は高齢層に集中している」と示されます。
例えば、世帯主年齢別の平均金融資産を例示すると以下の通りです。
-
29歳以下:約200万円(全体の約2%)
-
30〜39歳:約600万円(6%弱)
-
40〜49歳:約1,200万円(約12%)
-
50〜59歳:約1,800万円(約17%)
-
60〜69歳:約3,000万円(約29%)
-
70歳以上:約3,500万円(約34%)
合計すると60歳以上で全体の約63%を占めます。つまり、家計資産の増加は若年世帯よりも、高齢世帯が株式や投資信託を保有している効果が大きいのです。
なぜ高齢世帯に資産が集まるのか
理由はいくつか考えられます。まず、働き方です。今の高齢世帯は高度経済成長や安定雇用の時代を経験し、退職金も比較的厚かった世代です。さらに、金融危機やバブル崩壊をくぐり抜ける過程で「現金を多めに持つ」「投資は慎重に」という姿勢を持ちながら、結果的に資産を積み上げました。
次に、ライフイベントの時期です。住宅ローンや教育費が終わり、支出が減るタイミングで余剰資金が生まれ、それが資産として積み上がっていきます。私自身も子どもの教育費が落ち着けば、資産形成により回せる金額が増えるはずだと感じています。
一方で、若年世帯は住宅費や教育費が重く、思うように資産を築けません。したがって、統計全体で見れば「資産は高齢世帯に偏っている」という現象が起きるのです。
資産形成の追い風と課題
家計資産の増加は一見すると良いニュースですが、すべての世帯が豊かになっているわけではありません。高齢層に資産が集中する一方で、若年層や子育て世代は余裕が少ない現実もあります。
私の家庭も教育費のピークを迎えており、毎月の収支は決して楽ではありません。積立額を以前より減らさざるを得なかったのも事実です。統計上は資産が増えていても、実感は人それぞれに大きく異なるのです。
私の家計に当てはめて考える
今回の統計を自分の家計に重ねると、資産全体が膨らむ時期にこそ冷静さが必要だと感じます。株式や投資信託が増えているときは、どうしても「まだまだいける」と強気になりがちです。
しかし、私の投資スタンスは「長期・分散・低コスト」。この方針を崩さず、毎月の積立を続けることが結局は一番安心につながります。総資産7,000万円台を維持している今も、守りを意識しながら投資を継続しているのは、老後の不安を減らすためです。
老後に向けて必要な視点
統計から分かるのは、個人の努力だけでなく、経済環境が資産形成に大きく影響するということです。インフレが進む中で、預貯金だけに頼るのは危険ですし、過度なリスクも避けたい。
結局のところ「逃げ切り戦略」として、自分に合ったバランスを見極めることが重要です。私の場合は新NISAを軸にしたインデックス投資をベースに、現金比率を一定程度確保してリスクを抑えています。
まとめ
日銀の統計で示された2,239兆円という家計資産の数字は、日本全体の蓄えの大きさを示す一方で、その内訳を冷静に見ると「リスク資産へのシフト」と「高齢世帯への偏在」が鮮明です。私たち50代サラリーマン世代にとっては、退職や老後を見据えた最後の資産形成期でもあります。
統計の数字に安心するのではなく、自分の家計の現実に即して投資と貯蓄をどう続けるかが問われています。将来の生活を守るために、今できることを粛々と積み上げていく。それが結局、逃げ切りへの最短ルートだと私は考えています。
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。