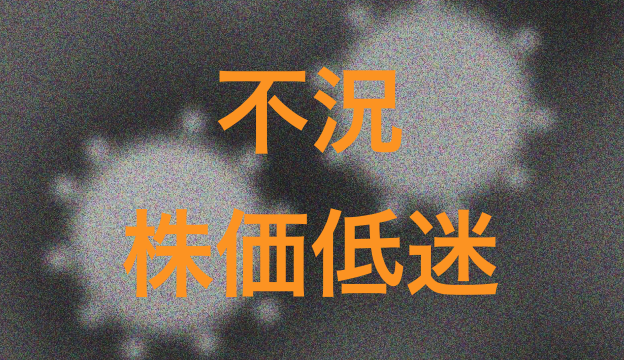日本全体の家計金融資産は過去最高の2,239兆円に達しました(日本銀行「資金循環統計 2025年6月末速報」)。
しかし、その内訳を見ていくと「豊かさの実感がない」理由が明確になります。
実は、60歳以上の世帯が日本の金融資産の約7割を保有しているのです。
若い世代が「貯蓄できない」「将来が不安」と感じるのは、努力不足ではなく構造の問題です。
この記事では、世代間で進行する“富の固定化”をデータで解説し、現役世代がどう行動すべきかを考えます。
1. 家計金融資産は過去最高、それでも「実感なき豊かさ」
日本銀行の最新統計によれば、2025年6月末時点の家計金融資産は前年比+4.1%の2,239兆円。
このうち現金・預金が約52%、株式や投信などのリスク資産が約20%。
つまり、半分以上が「動かないお金」です。
さらに、内閣府の『国民経済計算年報(2024年度)』によると、
60歳以上の世帯が保有する資産は全体の68%前後。
一方、40代以下の保有割合は20%台にとどまっています。
つまり、“資産大国”の実態は“高齢者資産大国”です。
出典:日本銀行「資金循環統計(2025年6月末速報)」
内閣府「国民経済計算年報(2024年度)」
総務省「家計調査(貯蓄・負債編 2024年)」
2. なぜ60代以上に資産が集中しているのか
(1) バブル期に資産形成のチャンスをつかんだ世代
現在の60〜70代は、バブル経済期に就労・昇進のピークを迎えた「勝ち逃げ世代」です。
株価上昇と地価高騰の恩恵を受け、退職金や不動産で資産を築いた人が多くいました。
一方、バブル崩壊以降に社会人となった世代は、低成長・デフレ経済の中で賃金が伸びず、資産形成の機会が限られました。
(2) 年金・退職金・持ち家の三重構造が強い
総務省の家計調査(2024年)によると、
60代の平均貯蓄額は1,947万円、30代では710万円。
しかも、60代世帯の約7割が持ち家(ローン完済済み)を保有し、年金収入で生活が安定しています。
つまり、生活コストが低く、資産を減らさずに済む層です。
一方、現役世代は住宅ローン・教育費・税金・社会保険料の負担が重く、
貯蓄余力がほとんど残りません。
同じ「平均年収600万円」でも、手元に残る可処分所得は過去20年で明確に減少しています。
(3) 相続が進まない「動かないお金」問題
内閣府の推計では、今後10年間で約1,000兆円規模の資産が相続対象になります。
しかし現実には、生前贈与を積極的に行う家庭は全体の2割程度。
多くの資産は高齢層で滞留し、若い世代に流れません。
背景には「相続税の複雑さ」「老後不安によるため込み」「金融知識の不足」などがあります。
結果的に、高齢者は資産を使わず・動かさず・減らさないまま寿命を迎え、
格差の連鎖が次世代に引き継がれています。
出典:内閣府「高齢化社会白書(2024年度)」
野村総研「富裕層調査2023」
(4) 高齢者が消費しない社会の副作用
日本経済の低成長の一因は「お金が使われないこと」。
60代以上は平均して年間支出が約300万円前後(総務省データ)と、
可処分所得に対する消費割合が若年層よりも低い傾向にあります。
つまり、資産を保有していても消費に回らない構造が続き、
景気刺激の効果が限定されているのです。
3. 格差の本質は「世代間の非対称性」
現役世代(30〜50代)は、社会保険料や税金で上の世代を支える立場にあります。
しかも、自身の年金は減る見通し。
「支える人」が減り、「支えられる人」が増える社会で、
現役世代が報われにくくなっているのは当然です。
例:年収600万円世帯の手取りは約470万円(社会保険+税で約130万円減)
一方、年金受給者の多くは課税軽減措置で実質的な負担が軽い。
つまり、格差の本質は「所得」ではなく「世代間構造」にあります。
これを理解せずに“努力不足論”だけが強調されるのは危険です。
現役世代は、制度と構造の歪みを前提に、自分の戦略を持つことが求められています。
4. 現役世代が取るべき3つの戦略
① “貯める”から“持つ”へ
現金預金だけではインフレに勝てません。
金利0.001%の預金では、物価上昇3%の時代に資産が目減りしていきます。
まずは新NISA・iDeCoなどの非課税制度を最大限に活用し、
株式・投信など“働く資産”を持つことが第一歩です。
② “相続を待つ”ではなく“キャッシュフローを作る”
親の遺産を当てにするより、自分のスキル・収入源を作ること。
副業・資格・配当など、少額でも定常的に収入を生む仕組みを作れば、
将来の「不安定な老後」に備えられます。
③ 金融教育を「自分ごと」にする
富の偏在は知識の偏在でもあります。
投資リテラシー・税金・社会保障の基礎を理解すれば、
「損しない行動」が取れるようになります。
金融庁の「つみたてNISA公式サイト」や「家計の金融行動に関する調査」は
信頼できる学びの出発点です。
5. それでも希望はある
日本は依然として、世界第3位の経済規模と豊富な家計資産を持つ国です。
つまり、“お金そのもの”は存在している。
問題は、それが動かないこと、そして若い世代が触れられないこと。
しかし、新NISAやiDeCoの普及で、
20〜40代の投資参加率は着実に上昇しています(金融庁2025年調査)。
時間を味方につける積立投資や副収入づくりを続ければ、
「世代間の不利」は少しずつ縮められる可能性があります。
大切なのは、社会構造を嘆くことではなく、
自分の老後を“受け取る側”ではなく“作る側”として捉えることです。
まとめ
日本の家計金融資産は過去最高を更新していますが、
その7割を保有しているのは60代以上の世帯です。
富が一部の高齢層に固定されることで、
若い世代は資産形成のスタートラインにすら立てない現実があります。
しかし、制度と環境を理解すれば、
“自分の経済圏”を築くことは決して不可能ではありません。
長期・分散・継続の力を信じて、今から資産を動かし始めましょう。
未来の不安を減らす最良の方法は、行動で「自分の富」を作ることです。
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。