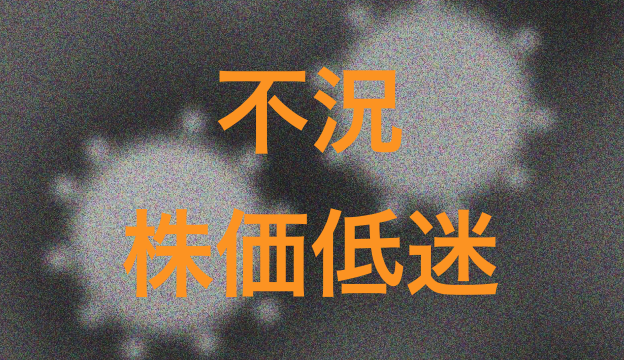デフレの終わりに備える|現金は本当に安全か?【2025年版】
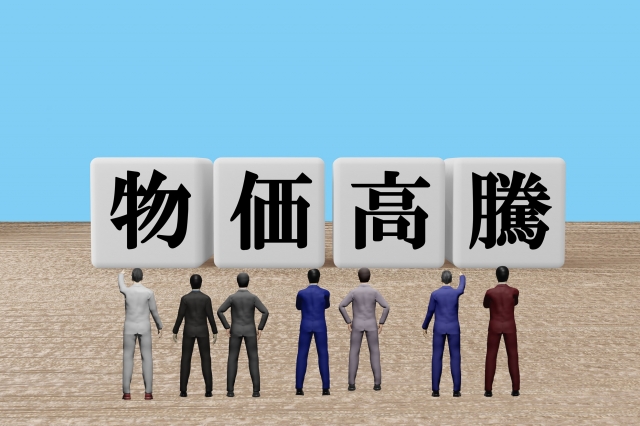
長く続いたデフレの時代が、ようやく終わりを迎えようとしています。
2020年代初めまで「物価が上がらない国」と言われ続けた日本も、近年はスーパーでの値上げや、外食の価格上昇を実感するようになりました。アベノミクスの金融緩和から10年以上、ようやく物価が動き始めたのです。
私自身、50代のサラリーマンとして長い間「現金は安全」と思ってきました。しかし、今の時代はその考えを見直すタイミングに来ていると感じています。この記事では、デフレ期に現金保有が有利だった理由と、インフレ期に起こる“現金の目減り”について整理しながら、これからの資産防衛の考え方をまとめます。
デフレ期に「現金が正義」だった理由
日本は約20年にわたり、物価が上がらないデフレ経済が続いてきました。
企業は価格を上げられず、給料も伸びず、結果としてお金の価値が下がらない――つまり、現金を持っているだけで実質的に得をする時代でした。
たとえば100円で買えた商品が、翌年には95円になる。これは「現金の価値が上がる」状態です。金利がほぼゼロでも、物価が下がれば貯金しておくだけで購買力は高まります。こうした環境では、普通預金が“無難で合理的”な選択だったのです。
私も長年、給与から一定額を定期的に貯金してきました。投資は怖いもの、という感覚が根強く残っていたのも事実です。
2025年、日本は「ゆるやかなインフレ」へ
しかし今、状況は変わりつつあります。
2024年の消費者物価指数(CPI)は前年比2%前後で推移し、2025年も食品・日用品を中心に値上げが続いています。政府・日銀が長年目標としてきた「物価上昇率2%」は、ようやく現実になりました。
さらに、日銀は2024年春にマイナス金利政策を解除。長期金利は1%台に上昇し、定期預金の金利もわずかに上向き始めています。とはいえ、物価上昇に比べれば金利上昇のペースは遅く、現金をそのまま持つことが“実質的な損”になる時代が近づいていると感じます。
インフレでは現金が目減りする
インフレとは「モノの価値が上がり、お金の価値が下がる」現象です。
たとえば毎年2%ずつ物価が上がれば、10年後には100万円の価値が実質的に約82万円にまで減る計算になります。これは“銀行口座の数字”が減るわけではなく、同じ100万円で買える量が減るという形で現れます。
このように、デフレでは守りになった現金も、インフレではリスク資産に変わります。
現金を持つ意味は「生活防衛資金」としての役割に限定し、残りは働く資産へ振り向けることが重要です。
現金は「必要最小限」でいい
私は今、総資産が約7,800万円ほどありますが、現金は260万円ほど。
比率にするとわずか3〜4%程度しかありません。これだけ聞くと「少なすぎる」と思われるかもしれませんが、目的を明確にしていれば問題はありません。
その260万円は、急な出費に備える「生活防衛資金」として確保しています。
仮に家電の買い替えや親の介護の追加費用、子どもの学費の値上げなど、想定外の支出が発生しても対応できる金額です。
それ以外の資金は、新NISA口座を通じて、世界株インデックスやS&P500などの長期投資に回しています。
インフレ時代の資産防衛術
インフレ環境では、現金を増やすより“お金に働いてもらう”方が合理的です。
ただし、闇雲にリスク資産を増やすのは危険。ここで大切なのは「守りと攻めのバランス」です。
-
守り(短期資金):生活費3か月分〜6カ月分の現金を確保
-
攻め(中長期資金):投資信託・ETF・年金積立などに分散
-
つなぎ(流動資産):高金利普通預金や個人向け国債などを一部活用
特に50代になると、退職金や相続などで大きな資金が入る可能性があります。そのときに“すべてを普通預金に置く”のはもったいない。時間を味方につけるためにも、少しずつ投資に慣れていくことが大切です。
「現金=安心」という時代は終わった
長いデフレを経験してきた世代ほど、「現金こそ安心」と思い込みがちです。
しかし、今の日本では「現金だけでは安心できない」状況に変わりつつあります。
物価が上がり続ける一方で、預金金利はまだ微増。つまり、銀行に預けたお金が“静かに目減りしていく”のです。
もちろん、すべてを投資に回す必要はありません。
大切なのは、時代に合わせて“現金と資産運用の比率”を調整すること。
それが、これからのインフレ時代における最も現実的な防衛策だと思います。
まとめ:デフレの記憶を引きずらない
私たちは、長いデフレを生き抜いてきました。
安定を重んじる考え方は正しいですが、時代は確実に変わっています。
今求められるのは、「安全第一」ではなく「柔軟なリスク管理」です。
現金を持ちすぎず、投資も無理をせず。
そのバランスを取ることこそ、老後不安のない“逃げ切り戦略”につながると感じています。
デフレの終わりは、資産運用の“再スタート”の合図なのかもしれません。
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。