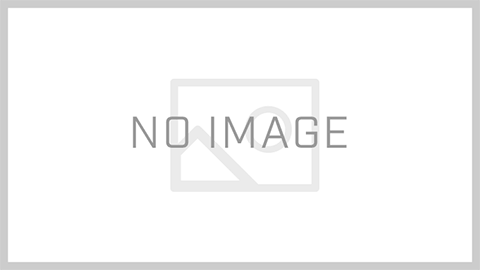【株主優待は本当にお得?】制度の3つの問題点と、米国株に投資先を変えた理由

日本株の魅力の一つとしてよく取り上げられる「株主優待」。食品や外食券、クオカードなど、つい惹かれてしまう人も多いのではないでしょうか。
実際、証券会社のサイトやマネー誌では毎月のように「今月の株主優待銘柄」「優待利回りランキング」などの特集が組まれています。
しかし私は、株式投資を学ぶ中でこの制度に違和感を持つようになり、最終的には日本株中心から米国株中心の投資スタイルへと移行しました。
この記事では、株主優待のどこに問題があるのか、なぜ米国株にはそのような制度が存在しないのか、投資家目線で整理しながらお伝えします。
株主優待制度とは?日本独自の“馴れ合い文化”
まず前提として、株主優待は日本特有の制度です。
企業が自社製品や割引券などを株主に贈ることで、個人株主を増やし、長期保有を促す目的があります。持株会や個人投資家が増えれば、敵対的買収に対する防波堤になるというメリットもあるのです。
しかし、こうした制度は本来の「株主平等の原則」に照らすと、決して透明とは言えません。
株主平等の原則:すべての株主は、その保有株数に応じて平等に扱われなければならない(会社法第109条)
ところが実際には、少数株主だけが優遇され、大口保有者は事実上無視されるという、歪な仕組みが放置されています。
私が感じる「株主優待の3つの問題点」
① 少数株主の優遇:株主平等の原則に反する
多くの優待制度は「100株〜300株の保有者」を優遇し、それ以上の保有に対してはインセンティブが少ないか、上限を設けて打ち止めにしています。
例えば、100株保有している人と1,000株保有している人が、まったく同じ優待しか受けられないというのは、保有株数に応じた平等性を欠く制度設計です。
これは、株主平等の原則に明確に反しており、持ち株数が多い株主ほど不満を抱きやすい構造になっています。
② 投資信託の購入者には恩恵がない
近年は個別株ではなく、投資信託やETFを通じて株式市場に投資する人が増えています。
しかし、株主優待は「個人名義で直接株を保有している人」しか受け取れません。つまり、投信経由の株主は事実上、優待の恩恵から除外されているのです。
もちろん、信託会社が優待を現金化してファンドに組み込むケースもありますが、手間もコストもかかり非効率ですし、現物優待(お米券や飲食券など)の換金は現実的に難しいものもあります。
それならば、素直に配当で還元すべきなのでは?という疑問が残ります。
③ 会社の費用計上→利益圧迫→株価下落の懸念
株主優待は企業にとって「販促費」「交際費」「株主還元費用」などとして費用計上されます。
当然、その分だけ純利益が減り、結果として1株あたり利益(EPS)が下がる可能性があります。
EPSが下がれば、P/Eレシオの水準によっては株価にマイナスの影響が及ぶこともあるわけです。
株主として得をしているようで、実は自分たちの持ち株の価値を削って優待を受け取っているという、逆転現象が起きているとも言えるのです。
なぜ米国株には株主優待がないのか?
非常にシンプルです。
米国では「株主への還元は現金(配当)で行うべきもの」という考えが徹底されており、優待のような“情緒的な仕組み”は投資と無関係という合理主義が浸透しています。
また、米国では株主が経営者を強く監視する文化があり、「会社の利益をどう還元するか」は明確に説明責任を問われます。
「現物の優待を出すぐらいなら、その分の配当を増やせ」と株主から突き上げを受けることも普通にあります。
つまり、資本主義の原則に忠実な形で株主還元が行われているということです。
私が米国株中心に移行した理由
私自身、かつては日本株中心にポートフォリオを組んでいました。特に投資初心者の頃は「優待利回り」や「○月優待銘柄」といった特集に惹かれ、いくつかの銘柄を保有した経験もあります。
しかし、次第に日本企業の株主との距離感のある経営姿勢や、不透明なガバナンスに疑問を持つようになりました。
さらに、世界的な経済回復局面でも日本株だけが取り残される「出遅れ」が繰り返される状況を見て、「これは構造的な問題なのでは」と感じたのです。
それに比べ、米国株は企業の説明責任・株主意識の高さ・成長性のある市場環境といった点で、より納得感のある投資ができると判断しました。
最後に:制度の本質を理解して選ぶ
株主優待制度は日本独特のものであり、うまく活用すればお得に感じる場面もあるでしょう。
私もこの制度を全面的に否定するわけではありません。制度が存在している以上、投資家として上手に使うのは賢明な戦略だと思います。
しかし、その裏にある「株主平等性の欠如」や「配当と優待の本質的違い」を理解した上で、投資判断を下すことが重要です。
優待目当てで集中投資をしてしまい、本来の分散投資や資産形成の原則を見失ってしまうことがないよう、慎重に判断していきたいところです。
👉 【実体験】USMHの株主優待を夫婦でダブル取得!優待券か商品か、選べる楽しみも魅力!
👉 株主優待目当ての投資で気を付けること。株主優待は改悪、廃止のリスクがある。
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。