暴落で学んだ長期投資の行動ルール|実体験から検証
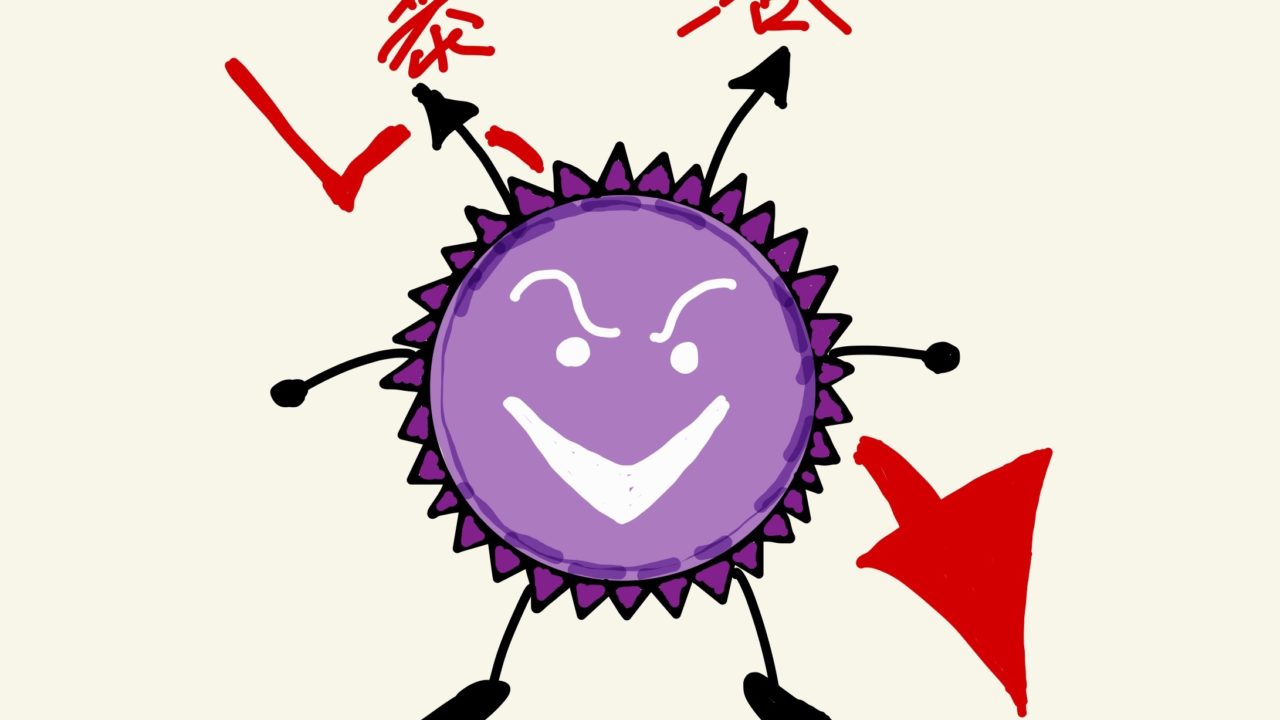
※本記事は2020年1月の投稿を、2025年8月17日に全面リライトしたものです。あの時の判断を検証し、今後の“暴落時の行動ルール”を整理しました。
2020年の恐怖を、いまの視点で読み解く
2020年1月27日、日経平均とTOPIXは大きく下落しました。最大の原因は「全貌が見えない不確実性」。移動制限や工場停止が相次ぎ、ニュースの更新に心が揺さぶられました。いまでこそ冷静に言えますが、当時の私は画面の赤い数字に毎日疲弊していました。
私の失敗:N225連動ETFを短期で“つまみ食い”
正直に書きます。私は日経225連動ETFを約300万円、短期で利ざやを狙って買いました。「すぐ戻るだろう」と思い込んでいたのです。ところが相場はさらに下へ。ルールから外れた行動は、例外なくメンタルを削ります。
値動きに振り回され、夜中までチャートを見続け、家族との会話も上の空。長期投資家を自認していたのに、私自身が“タイミング売買の罠”に落ちました。
その後:持ち続けた結果、含み損は含み益へ
結論から言えば、私は積立と分散、年1回のリバランスを崩さず続けたことで、評価額は含み損から含み益へ転じました。勘が当たったわけではありません。やるべきこと(積立・分散・リバランス)を続け、やらないと決めたこと(短期の売買)を封印しただけです。
価格は読めない。でも、買い続けた口数は裏切りません。この実体験は、今の私の投資の“芯”になっています。
暴落時の行動ルール(私のチェックリスト)
・積立は止めない。金額調整はあっても“停止”はしない
・リバランスは年1回、または目標配分から±5%乖離で機械的に実施
・商品は増やさない。迷いを増やすほど次の下げでブレる
・ニュース閲覧は1日2回まで。プッシュ通知は基本オフ
・価格が気になったら、証券口座ではなく家計簿を開く(生活の見える化)
・どうしても不安が強い時は、全世界株の比率を少し上げてボラティリティを下げる
分散の作法:S&P500派でも“1段”広げる
私はS&P500中心ですが、地域偏りのリスクは常に意識しています。慎重派は全世界株インデックスを少量混ぜるだけで、通貨・国・セクターの偏りが和らぎます。
個別株やテーマ型に寄せすぎると、ショック時の下落と回復の差が大きく、精神的にもたない場面が増えます。“勝ち筋”は派手さではなく、続けられる配分にあると痛感しました。
50代の家計と投資:現金比率は“役割”で決める
私の現金目安は5%前後。暴落時に慌てて現金を厚くするのではなく、学費や介護などの年間カレンダーに合わせて平時に確保します。
生活は生活、投資は投資。役割を分けるほど相場に振り回されません。入金力が落ちた時期は、積立額を事前に下げてでも枠は継続します。非課税の“時間”は戻ってこないからです。
次の下げまでにやっておく5つの設定
-
積立設定は翌年分まで予約して、変更を“面倒”にする
-
リバランスのしきい値(±5%など)を紙に書いて机に貼る
-
生活資金は別口座で先取り。投資口座からの引き出しを禁じる
-
価格アラートは月1回の大まかな帯だけにし、細かい通知は切る
-
暴落時のToDoテンプレを用意。「やる=積立確認」「やらない=新商品の追加・信用取引」
なぜ“停止しない”のか:時間分散は下げ相場ほど効く
価格が落ちている時ほど、同じ金額でも多くの口数が買えます。積立を止めるのは、安く仕入れられる時期を自分から拒否すること。私はコロナ急落の局面で、積立設定に手を触れませんでした。
毎月の約定メールが届くたびに「安く買えた」と小さくガッツポーズをし、翌月も粛々と続ける——この地味な継続が、のちの含み益を支えてくれました。
メンタルを守る3つの工夫
-
価格アプリをスマホの2ページ目以降へ移動し、ワンタップで開けないようにする
-
見るニュース源を2つに限定し、SNSの投資トレンドは見ない日を作る
-
「やる・やらないリスト」を紙に書き、暴落時に読み上げる習慣をつける
リバランスの現場感:私の基準
私の目安は年1回または乖離±5%。例えば株80%・現金5%・その他15%が目標なら、株が85%に膨らんだ時に少しだけ売って配分を整えます。
逆に株が70%に落ちたら、現金から株に振り向ける。大事なのは“感情”ではなく“配分”で判断すること。結果として高くなったものを売り、安くなったものを買う動きになります。
「家計の不確実性」を先に片づける
相場の不安の正体は、実は家計の不安であることが多い。だから私は、1年の学費や更新料、帰省、家電買い替えなどを一覧化し、月ごとに見えるようにしています。
出ていくお金が見えていれば、相場が荒れても生活の土台は揺れにくい。投資口座に手を付ける誘惑も減ります。
小さな実例:下げ相場で口数が積み上がるイメージ
仮に毎月1万円を同じ投信に積み立てるとして、基準価額が1万円→8千円→1万円と推移したとします。下げた月には多くの口数が買え、回復時にはその口数が効いて評価額が戻りやすくなる。
単純化した例ですが、時間分散の本質はここにあります。私はこの“口数の積み上がり”を信じて続けました。
将来の自分への手紙(テンプレ)
次に相場が大きく荒れたら、この文章を読み返してください。
・積立は止めない。ルールは君を守るためにある
・今の不安は“価格”ではなく“生活”に由来していないか、家計のカレンダーを見よ
・商品を増やすな。過去の自分が選んだ配分を信じよ
・眠れないなら、全世界株を1段増やしてよい。ただし一度増やしたらしばらく固定する
50代のリアルと両立するために
私は出世組でもなく、普通の平社員です。家族の学費や親の介護費が重なる月もある。そんな私でも投資を続けられたのは、完璧を求めなかったから。額は上下しても、仕組みだけは止めない。これが長く続けるための“現実解”でした。
もう一度、結論
暴落の最中に「何もしない」は勇気が要ります。でも、最初から“何もしないで済む設計”にしておけば、勇気はほとんど要りません。
自動積立、分散、年1回のリバランス、別口座の生活資金。これらは地味ですが、将来の自分を助けてくれる最良の味方です。
まとめ
暴落は読めません。だからこそ、積立を止めない、分散を1段広げる、生活資金は別に置く——この3点を“仕組み”に落とし込みます。私はコロナ急落時に短期売買でつまずきましたが、最終的にはルールを守って持ち切ったことで報われました。
次の下げでも、やることは同じ。口数は裏切らない。派手な予想より、地味な継続が資産を作ります。
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。


















