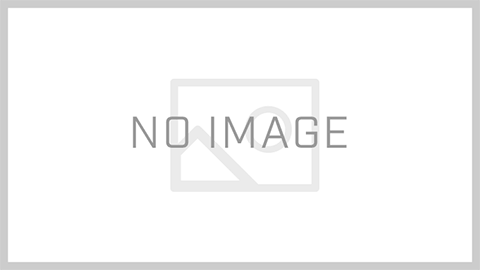「準富裕層」という言葉を聞くと、どこか別世界の人たちの話のように感じる人も多いだろう。
しかし、野村総合研究所(NRI)の定義では、金融資産7,000万円以上1億円未満の世帯がこの層に該当する。
私自身、長年の節約と積立投資を続けてようやくその水準に到達したが、正直な感想を言えば「思っていたほど裕福ではない」。
むしろ、「ようやく老後破綻を回避できるかもしれない」というラインに立ったに過ぎない。
準富裕層=7,000万円の意味と位置づけ
NRIの調査によると、2023年時点で準富裕層は日本全世帯の約6%。
上位10世帯に1世帯程度しかいないため、数字上は“特別な存在”に見える。
しかし実際には、退職金や持ち家の評価額を含む「総金融資産ベース」で算出されるケースが多い。
現金・投資信託・株式などの“運用可能資産”だけで7,000万円を超える人は、体感的にはもっと少ない。
私の場合、住宅を所有しておらず、賃貸生活を続けている。
したがって、資産の大半は投資信託と預貯金だ。
一見すると流動性の高い安心資産に見えるが、老後も家賃を払い続けることを考えると、決して気楽ではない。
7,000万円を保有していても、毎月15万円前後の固定費が継続して出ていく現実を前にすると、「安心」とは言い難い。
生活感のリアル:「余裕がある」より「減らさない努力」
私の家計は、毎月の手取りは少ないので、教育費や家賃を差し引けば、可処分所得は多くないです。
それでも家計を黒字で維持できているのは、節約を習慣にし、ムダな支出を減らしてきたからだ。
食費や光熱費も上昇しているが、我が家では「1割削るより、1割稼ぐほうが難しい」と実感している。
資産7,000万円と聞けば、周囲から「もう十分じゃない?」と言われる。
だが、老後30年・月25万円の生活費を想定すると、必要総額は約9,000万円。
そこから税金や医療費、介護、子どもへの援助などを引けば、7,000万円は“余裕資金”どころか「ぎりぎり逃げ切れるライン」だ。
統計と現実のズレ:インフレと長寿化の影響
2020年代に入り、日本でも年2〜3%のインフレが続いている。
10年で約2割、生活コストが上がる計算だ。
つまり、今の7,000万円は10年前の5,000万円台の価値に相当する。
さらに医療の進歩により寿命が延びたことで、「お金を持つ期間」が以前よりも10年以上長くなっている。
この環境下で、私はつみたてNISAを中心に世界株インデックスへ分散投資している。
リターンの平均値は年3〜4%だが、心がけているのは「暴落時に動かないこと」。
上がっても下がっても淡々と積み立て続ける——この地味な継続力こそ、最終的に資産を守る最大の武器だと痛感している。
「準富裕層=安心」とは限らない3つの理由
1つ目は「リスク許容度の低下」。
資産が増えるほど減ることへの恐怖が増し、必要以上に守りに入ってしまう。
結果的に現金比率を高めすぎ、インフレに負けるパターンが多い。
2つ目は「税負担の上昇」。
配当・分配金・売却益に課される税率20%超は、資産が増えるほど重くのしかかる。
特に社会保険料への影響も加わり、思った以上に可処分収入は減る。
3つ目は「心理的疲労」。
7,000万円を守るプレッシャーは意外に大きい。
一度下落を経験すると、「この資産を失いたくない」という思いが強くなり、精神的にはむしろ不安定になることすらある。
私自身、2022年の株価下落で含み損が1,000万円を超えたとき、夜中に何度もスマホでチャートを確認していた。
結果的に売らずに持ち続けたが、「資産がある=心が安定する」とは限らないことを身をもって知った。
7,000万円から“逃げ切る”ための5つの戦略
私がこれから意識しているのは、単なる運用ではなく「持続可能な家計管理」だ。
-
取り崩し率を年3%以内に抑える。
4%ルールを鵜呑みにせず、現実的な日本型シミュレーションで考える。 -
支出を“固定化しない”。
保険・通信費・サブスクなど、年1回見直すだけで生涯支出は数百万円変わる。 -
インフレ資産を一部組み入れる。
米国ETFや全世界株ファンドで物価上昇への耐性を確保。 -
働けるうちは働く。
副業やパートでも、年100万円の追加収入は資産寿命を大きく延ばす。 -
時間資産を優先する。
お金を使う目的を「安心」から「体験」に変える。
健康と人間関係に投資するほうが、結果的に幸福度は高い。
“準富裕層”の落とし穴と次世代への視点
資産を築いた後に意外と悩むのが、「使い方」と「継承」だ。
50代後半になると、子どもに少しでも遺したい気持ちが芽生える。
だが、教育・住宅・結婚と支援を重ねると、あっという間に数百万円単位で資産は減る。
“助けたい”という気持ちが、老後資金を削るリスクにもなり得る。
また、相続や贈与を考える際、現金を残すより「金融リテラシーを残す」ほうが重要だと最近は感じている。
どれだけの資産を築いても、子世代がその運用を理解していなければ、短期間で減らしてしまうこともある。
7,000万円という数字よりも、「お金との付き合い方」を家族で共有することが、真の“富の継承”かもしれない。
結論:7,000万円はゴールではなく、再スタートの数字
準富裕層という呼び名は響きがいいが、実際には「ようやく安心の入口」に立った段階だ。
インフレ・税金・寿命の伸びを考えれば、守り抜く努力が欠かせない。
7,000万円は“逃げ切りの起点”であり、老後の生活をデザインするための基礎体力にすぎない。
これからも私は、派手さより堅実さを重視しながら、「お金に振り回されずに生きる力」を磨いていきたい。
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。