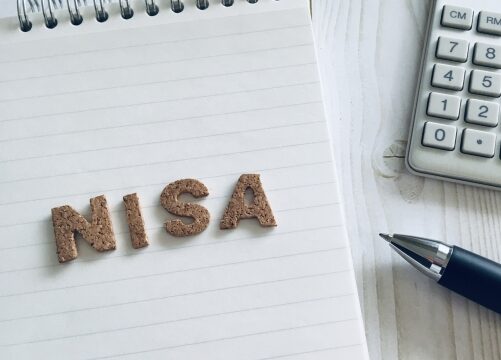はじめに:50代、貯蓄額が気になる時期
私(50代サラリーマン・役職なし)は、賃貸暮らし・住宅ローンなしという立場で、子ども2人(高校3年生・中学2年生)を抱えながら「このままで老後は大丈夫か」を常に考えています。家計支出も教育費・住居費・生活費が重くなりやすく、しかも「貯蓄できているのか」「他の人はどうなのか」をつい比較してしまう年代です。今回は、特に「50代サラリーマン」という視点から、貯蓄額のリアルを“平均値”だけでなく“中央値”という切り口でも見てみます。とは言え、私のような投資初心者~中級者にとって“平均値”だけでは実感が湧かず、むしろ“中央値”の方が現実に近い指標になります。
50代の貯蓄額ってどのくらい?最新データをチェック
まず、データを押さえておきましょう。
– 「金融広報中央委員会」による調査では、50代(単身世帯)の貯蓄の平均値が 約1,391万円、2人以上世帯で 約1,147万円 という報告があります。三井住友銀行
– ところが、同じデータで50代の“中央値”は、単身世帯で 約80万円、2人以上世帯で 約300万円 と大きく低く出ています。マネプロ
この開きが意味するものは何か。「平均値」は一部の極めて貯蓄が多い世帯に引き上げられており、50代世帯の“典型的”な姿を示していない可能性があるということです。
例えば、別の調査では50代世帯の中央値を「約600〜700万円」とするものもあります。資産運用はじめるならマネイロどれを採るかで読み取り方も変わりますが、大事なのは「中央値を意識すること」です。
平均値だけ見て“安心”してはいけない理由
では、なぜ“平均”と“中央値”にこれだけ差が出るのでしょうか。主な理由は以下です。
-
貯蓄ゼロ・ごく少額の世帯も一定数存在する一方で、数千万円・数億円と資産を築いている世帯が平均を大きく押し上げる。
-
世帯構成・収入の幅・資産運用歴などが大きく異なり、50代でも“貯蓄格差”が拡大している。実際、50代の貯蓄の開きが目立つという調査もあります。Sony Life
-
“平均値”をもって「我が家もほぼ平均近い」と考えてしまうと、実態よりも安心してしまうリスクがある。
実際、50代の2人以上世帯で中央値が300万円という数字は、「多くの世帯が貯蓄300万円程度しかない」可能性を示しています。平均1,100万円超という数字だけを見て安心するのは、やや危うい見方です。
私もかつて「平均を目安にしよう」と思っていましたが、妻と相談して現実値を把握していないことに気づき、「中央値をひとつの基準にしよう」と方針を変えました。
50代サラリーマン世帯の私の場合と“逃げ切り”戦略
ここからは、私のケースを交えて“50代サラリーマンの貯蓄実態”を見つつ、今後どう資産を活かしていくか考えます。
私の貯蓄・投資スタンス
私は、総資産が7,000万円台という準富裕層とされる範囲にいますが、それでも“油断すれば月5万円赤字”になります。なので、支出やリスクを甘く見るわけにはいきません。賃貸暮らしで家賃が固定費としてあり、子どもの教育費もあと数年は続きます。投資は「長期・分散・低コスト」+新NISA主体、レバレッジや信用取引は使わず、FIREよりも「逃げ切り戦略」「老後の安心」を重視しています。
「中央値」を基準にした見直し
多くの50代世帯では貯蓄300万円あたりという中央値が報告されています。私の場合はそれを大きく上回り、総資産7,000万円台という準富裕層の立場にいます。しかし、それでも「老後まで安心」とは言い切れません。教育費や生活費、将来の医療・介護、年金減少などを考えると、油断できる状況ではないのです。
そこで私が取った戦略は次の通りです:
-
支出を「老後2,000万円問題」から実感へ落とし込む。家計見直し、固定費削減、賃貸ならではの流動性を活かす。
-
資産を「貯める」段階からはすでに卒業し、いまは「運用しながら取り崩す」フェーズを意識しています。
現金比率は5%以下、ほぼ全額を投資に回していますが、生活防衛資金を確保しつつ、インデックス投資を中心に配当や分配金を再投資。
“減らさずに使う”を目指し、資産の寿命を延ばす運用設計にしています。 -
リスク許容度を意識し、短期売買・ハイリスク戦略は避けつつ、ドルコスト平均法で積み立て継続。
-
「逃げ切り」のためには、貯蓄額の絶対値ではなく、毎月の支出と資産収益率のバランスを重視。つまり「支出をカバーできる収益を作る」ことに注力。
このように、自分の立ち位置(50代・賃貸・子どもあり)を踏まえて、中央値を“下回らない”ことをまず目標にし、次に「貯蓄額を増やす」ではなく「貯蓄を活用する」フェーズに移行しています。
50代から取り組むべき“次の一歩”
50代からでも「今からでも遅くない」取組みはあります。以下、私が実践し効果を実感しているものです。
支出の見える化と削減
賃貸暮らしという条件を活かし、「住居固定費を大きく抱え込まない」「賃貸ならではの撤退・引越し選択肢を残す」ことを前提にしています。また、家計簿アプリ・毎月の支出見直し・通信・保険など「固定費削減」から入りました。これは貯蓄額が少ない場合にも即効性があります。
資産の「守りと攻め」の配分
私の場合、資産の80%を「守り」としてインデックス投資・低コストファンドで運用し、残り20%を「攻め」として成長株・米国株・優待株を少額ながら組み込んでいます。50代であるため、リスクを取りすぎないよう、信用・レバレッジは避けています。
“逃げ切り”マインドセット
「FIRE(早期リタイア)」を目指すわけではなく、「定年後・収入減少後も安心できる生活基盤」を構築する“逃げ切り”戦略を採用しています。貯蓄額だけで安心せず、「資産からの収益(分配・配当)+社会保障+働ける余力」で構えるのが現実的だと考えています。中央値・平均値いずれも参考にしつつ、自分自身の数字に落とし込むことが重要です。
まとめ:50代の貯蓄実態を知って、自分の戦略に活かそう
今回ご紹介したように、50代サラリーマン世帯の貯蓄額には大きなギャップがあります。平均値だけを見ると「1,000万円超」などと頼もしい数字が出ていますが、中央値では「数百万円」という現実も浮かび上がります。つまり、多くの世帯は平均に届かず、貯蓄ゼロ・少額のままという可能性もあるわけです。
私自身、賃貸・子ども2人という状況の中、「中央値を下回らないこと」を最初のハードルとし、次に「資産を活用して収益を生む」ことを目指してきました。50代からでも、貯蓄額だけで判断せず、自分の支出・資産・収益の三つをバランスよく考えることで「逃げ切り」の道筋は描けます。
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。