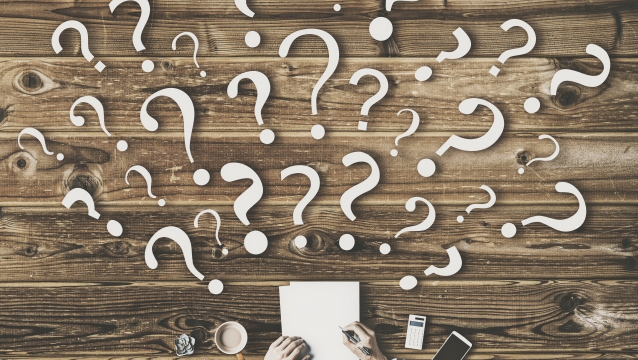イオン株主優待とラウンジ制度の本音レビュー|2025年版

イオンは日本を代表する流通大手として、個人投資家からも高い人気を誇っています。中でも100株から始められる株主優待制度「イオンオーナーズカード」は、日常の買い物に直結する実利が魅力です。
この記事では、2019年当時の株主総会やラウンジの実体験を振り返りつつ、2025年現在の制度や課題について、投資家としてのスタンスから率直にリライトしました。
イオン株主総会には行かなかったけれど…
2019年5月29日、イオンは株主総会を開催しました。参加者は2,000人近くに上る大規模なもので、個人株主の多さを象徴しています。私もイオンの株を長年保有していますが、この総会には参加しませんでした。
株を購入したのは、投資初心者だった頃。イオンが生活圏にあり、イオンクレジットカードも使っていたため、馴染みある企業に投資したいと思ったのがきっかけです。
以来、株価の値動きに一喜一憂することなく100株を保有し続けています。イオン株は優待制度の人気もあって、今も個人投資家にとって根強い支持を集めています。
イオンオーナーズカードとラウンジの実態
イオンの株主優待では、100株以上の保有者に対してオーナーズカードが発行され、買い物額に応じたキャッシュバックが年2回受け取れます。さらに、株主にはイオンラウンジの利用資格も与えられていました(※2025年現在は抽選・制限付きで再開)。
私も以前、ラウンジを一度だけ利用しました。内容はというと、トップバリュブランドの飲料やお菓子が少々提供される休憩スペース、といったところです。空港のラウンジのような豪華さは一切なく、正直なところ「並んでまで入る価値はあるのか?」と感じました。
実際、2019年当時の株主総会では「ラウンジに30分以上並ばされた」という声が挙がっていました。
岡田社長はその場で「本年中に、株主のためのものか、お得意様のためのものか、どちらかにせざるをえない」と発言。利用者急増に制度が追いついていない現状が浮き彫りになりました。
株主優待制度の限界と私の考え
正直に言って、私は株主優待制度には反対派です。株主であるならば、平等に利益を享受すべきで、優待という“特典”はその原則に反しています。
特に日本株では、少数株主に手厚い制度が多く、逆に多くの株を保有している投資家が不利になることすらあります。たとえば、3,000株でも6,000株でももらえる優待が一律3,000円分のクオカード、というような仕組み。
一方で、優待の内容によって株価が左右されたり、改悪によって投資家が損をするケースも少なくありません。投資信託で保有している人には優待の恩恵も届かず、平等とは言えません。
私自身、こうした日本独特の株主軽視とも言える文化から、投資の中心を米国株にシフトしています。
それでもイオン株を保有している理由
ではなぜイオン株を今も保有しているのか? それは、イオンが生活に根ざした企業であること、そして自分自身が日常的に利用しているからです。
オーナーズカードによるキャッシュバックや、買い物での実利は「使う人にとっては価値がある」と実感できます。実際、2019年9月1日~2020年2月20日の間にイオンで376,985円を買い物し、11,350円のキャッシュバックを受け取ることができました。
当時はコロナ禍による家計への影響も大きかったので、家計支援としてはありがたいものでした。
まとめ:優待は「使える人が使えばいい」制度
株主優待に過度な期待をするのではなく、「あれば活用、なければ気にしない」くらいの距離感がちょうど良いのかもしれません。
私自身は今でも配当や企業成長を重視するスタンスですが、生活圏にイオンがある方にとっては、株主優待は日常にプラスをもたらす実利的な制度です。
ただし、くれぐれも優待目的での過剰投資にはご注意を。投資は冷静に、そして長期目線で臨むのが鉄則です。
※関連記事:
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。