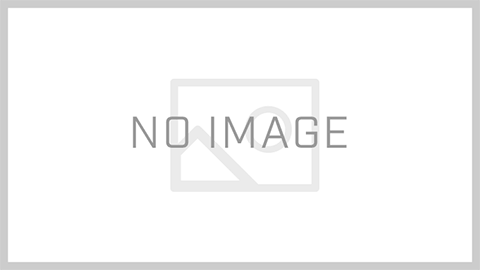ここ数年、「米国株こそ王道」「S&P500さえ積み立てていれば安心」といった言葉をよく耳にします。新NISAの導入により、米国株インデックスファンドの人気はさらに高まり、多くの個人投資家が米国市場に投資資金を振り向けています。
私も米国株には長年投資してきました。特にインデックスファンドを中心に、ドル建て資産をコツコツ積み上げてきました。しかし、2023年〜2025年にかけて、私はあえて「米国株の積立額を減らす」という選択をしました。
「米国株をやめたの?」と聞かれれば、答えは「いいえ」です。積立は続けていますが、比率と金額を調整して、日本株インデックスの割合を増やしているというのが正確なところです。
本記事では、その理由や背景、為替リスクの考え方、そして「米国株一辺倒」にならないための分散投資戦略について、私の実体験をもとに解説します。
米国株に投資を始めたのは「円高」の時代だった
私が米国株に本格的に投資を始めたのは、まだ1ドル=100円台前半だった頃。つまり、「円が強くて、ドルが安い時代」です。
当時は、「どうせ長期投資するなら、安くドルを買えるうちに米国株を仕込んでおこう」と考え、S&P500や全米株式(VTI)などのインデックスファンドを定期的に購入していました。
このときの判断は、自分なりに合理的なものでした。
-
為替の面で「円高」を活かす
-
成長性の高い米国企業群に分散投資
-
配当再投資による複利効果を狙う
こうして米国株投資は順調にスタートし、資産形成の一部を支える柱となっていきました。
2025年、円安が進行し、米国株が“高く感じる”ように
ところが、2022年以降、急速に円安が進行。2025年現在、1ドル=160円近辺という歴史的な円安水準にあります。
この為替環境の変化により、米国株に投資するコストが非常に高くなっていると私は感じるようになりました。
たとえば、以前なら1ドル=105円のときにVTIを購入していたものが、今は1ドル=160円という状況。仮に株価自体が横ばいでも、日本円に換算したときの購入コストは約1.5倍にも膨らんでいることになります。
つまり、高い通貨で、さらに高値圏にある株を買っている状態になっているのです。
SNSでは「円安だから米国株!」という声もあるが…
ここで一つ、よく聞く主張があります。
「円安だからこそ、外貨資産を持つべき!ドル資産を増やそう!」
この主張自体は一理あります。たしかに将来的にさらに円安が進めば、今のうちにドル資産を増やしておくことは有利に働くかもしれません。
しかし一方で、為替が反転し、円高になった場合の下落リスクも大きくなるのです。
株式投資の基本は「安く買って、高く売る」。為替が円安のときに米国株を大量に購入するのは、ある意味では「高値掴み」に近い行動でもあります。
もちろん、為替の未来は誰にもわかりません。だからこそ、一方向に資産を偏らせることの危うさを、私は強く感じるようになりました。
米国株の積立額を減らし、日本株を増やした理由
こうした考えから、私は2023年後半から徐々に米国株の積立額を減らし、その分を日本株のインデックスファンドに振り分けるようにしています。
日本株もインデックスを基本とし、TOPIX連動型や日経平均連動型の低コストファンドを活用。こうすることで、為替の影響を受けず、円建てで資産を積み立てることができます。
私が実践しているのは、
-
米国株:日本株=6:4 → 5:5 へ比率を調整
-
新NISAの成長投資枠を日本株にも分散
-
相場急落に備えて現金比率は最低限維持(5%以下)
といったスタンスです。
米国株をやめたわけではない。続けながらリスクを抑える
念のため補足しますが、私は米国株を完全にやめたわけではありません。毎月少額ながら、S&P500連動型のファンドは引き続き積み立てています。
理由はシンプルで、「もし今後も米国株がさらに上昇すれば、取り残されるのが嫌だから」です。
また、急激な円安が進行すれば、ドル建て資産の評価額が跳ね上がる可能性もあるため、完全にゼロにするのは避けたいのです。
いわば「攻めすぎず、守りすぎず」の中庸的なスタイル。これが今の私にとって最適なバランスだと感じています。
米国株一辺倒のリスク|分散投資の必要性
新NISAの人気銘柄ランキングを見ても、上位はほとんどが米国株インデックスファンド。たしかに過去の実績を見れば納得ですが、未来も同じように上がり続ける保証はありません。
さらに言えば、米国市場のリスクは以下のような形で表面化する可能性もあります。
-
FRBの利上げ再開や利下げ遅延
-
大統領選挙による政策不透明感
-
GAFAなどハイテク企業への規制強化
-
地政学的リスク(中東・中国・台湾)
そしてもう一つ忘れてはならないのが、為替リスクです。株価が上がっても、円高が進めば円ベースの資産価値は目減りする。これは米国株投資における宿命とも言えるリスクです。
だからこそ、私は日本株にも投資を続け、リスクを分散しながら着実な資産形成を目指しています。
「どこに投資すべきか」ではなく、「どう分散するか」が大切
投資において最も大事なのは、「どこの国が伸びるか」を完璧に予測することではなく、未来が読めないことを前提に、どう分散して備えるかです。
-
米国株だけでなく日本株にも
-
インデックスだけでなく一部現金や国債にも
-
円建て・ドル建てのバランスも意識
こういった全体最適を考えながら、ブレずに積立投資を継続することが、長期的な成功につながると私は信じています。
最後に|投資は「自分なりの納得感」が大切
ここまで書いてきたことは、あくまでも私個人の経験と考え方です。誰にとっても最適な答えではないかもしれません。
しかし、「なぜ今この投資をしているのか」「それは将来に向けて納得できる理由なのか」を自分に問いかけることが、投資を続けるうえでの一番の支えになります。
自分の軸を持ち、過熱にも悲観にも流されず、地道に積み上げていくこと。
それが、投資の王道だと私は思います。
この記事が、投資判断の一つの参考になれば幸いです。投資は自己責任です。ご自身のリスク許容度や資産状況に応じて、最適な判断をしてください。
関連記事
👉 50代・手取り20万円台でも資産7,200万円|“逃げ切り”老後戦略のリアル
👉 米国株だけに投資して大丈夫?2025年の今こそ分散投資を見直すべき理由
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。