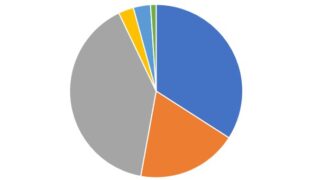「家は買うべきか、それとも賃貸でいいのか?」 これは多くの人が人生のどこかで直面する大きなテーマです。
20代や30代でこの選択に迫られ、判断を下した方も多いでしょう。しかし、50代に差し掛かると、過去の判断を改めて振り返る時期でもあります。そして、これから老後をどう暮らしていくのかという視点からも、「持ち家 vs 賃貸」の議論は再燃します。
この記事では、50代・4人家族・会社員の筆者が、賃貸を選び続けてきた実体験をもとに、「賃貸で良かったのか?持ち家を買うべきだったのか?」をリアルな視点で検証します。
持ち家 vs 賃貸|3つの視点で検証
【比較1】住宅ローン vs 家賃の支払い
持ち家:住宅ローン完済後も支払いは続く
住宅ローンは30〜35年と長期の負債ですが、完済しても以下の費用がかかります:
- 固定資産税
- 修繕費(外壁・屋根・水回りなど)
- 管理費・修繕積立金(マンションの場合)
つまり「ローン完済=住宅コストゼロ」ではありません。
また、住宅ローンには「住宅ローン控除」や「団体信用生命保険(団信)」といった制度もあり、若いうちに購入していれば所得税の控除や、万が一の際に残債が免除される安心感を得られたという意見もあります。
賃貸:家賃は一生必要。でも柔軟性がある
賃貸住宅は家賃がずっと続くという不安がある一方で、住み替えの自由度や生活の変化への柔軟な対応が魅力です。筆者も20年間で複数回住み替えを行い、家族のライフステージに応じて住まいを調整してきました。
【比較2】住まいの自由度と流動性
持ち家:資産になる一方で制約も多い
- 地価や不動産市況に左右され、売却が難しいことも
- 転勤、介護、離婚などライフイベントで柔軟性が求められる
- 修繕費や相続トラブルも懸念材料
賃貸:人生の変化に合わせて柔軟な選択が可能
- 親の介護にあわせて実家近くに引っ越す
- 子どもが独立後に家賃の安い物件へ移る
- 将来的には高齢者向け住宅(UR、サービス付き住宅など)へ転居
さらに、最近では「セーフティネット住宅制度」や「家族信託」など、年齢による賃貸不利を緩和する仕組みも拡大しています。
【比較3】老後の安心感は?
持ち家の安心感と落とし穴
完済済みの持ち家があれば、確かに老後の家賃負担はありません。また売却やリバースモーゲージで老後資金化も可能。
ただし、
- 建物の老朽化
- 周辺環境の変化
- 修繕負担や近隣トラブル
といった“持ち家ならではの問題”が見過ごされがちです。
賃貸でも老後は怖くない。そのための備えとは?
- 高齢者歓迎の物件、UR賃貸、公的住宅の活用
- 家賃保証会社の活用や連帯保証人の確保
- 生活費にゆとりを持たせる家計設計
さらに、将来のバリアフリー対応や医療アクセスの良さなどを優先した住み替えが可能なのも、賃貸の強みです。
筆者も将来に備えて、無理のない範囲で投資・貯蓄を継続しています。
【体験談】50代・子持ちサラリーマンが“賃貸暮らし”を20年続けたリアル
筆者は20年以上にわたり賃貸住宅に住み続け、持ち家は一度も購入していません。
メリット
- 家族構成や勤務先に応じて住み替えできた
- 修繕費や固定資産税の支払いがなく、家計を調整しやすかった
- 投資や教育資金に回す余裕が生まれた
特に、子どもが小さかった時期は教育費がかさみ、固定費を抑えられる賃貸は非常にありがたい存在でした。学区や通学距離、周辺の治安を考えて、柔軟に引っ越しできたのも大きな利点でした。
デメリット
- 老後の家賃負担が残る
- 高齢になると物件選びの制限が出てくる可能性
- “自分の家”という所有感がない
それでも、自分たちのライフスタイルには賃貸が合っていたと実感しています。
【結論】正解は「自分の人生の目的」から逆算すること
持ち家と賃貸、どちらが正解という絶対解はありません。 重要なのは:
「自分と家族のライフスタイルに合った住まいか?」
50代は「住宅に関する再設計」が必要な時期です。
- 子ども独立後の住まいを見直す
- 住宅費と老後資金のバランスをとる
- 老後の安心を得るための“家のあり方”を再考する
今からでも軌道修正は可能です。
- 賃貸の人は、老後に備えた家賃シミュレーションや物件リサーチを始める
- 持ち家の人は、住み替えや売却、リフォームも選択肢に入れる
- 家計を見直して、住居費に偏らないバランス設計を意識する
持ち家を持っている人も、賃貸の人も、今からの行動で将来は大きく変わります。
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。