【2025年最新版】なぜ今の20代はこんなにお金がないのか?若者の経済的苦境とその背景

1. はじめに:20代の若者が抱える経済的な苦しさとは?
2025年の日本において、「20代が経済的に苦しい」という現実は、もはや社会問題といっても過言ではありません。SNS上には「手取り15万円」「貯金ゼロ」「副業しないと生活できない」といった声があふれ、ニュースや行政報告でも若年層の生活困窮がたびたび取り上げられています。
これは単なる「若いうちは苦労するもの」というレベルを超えた構造的な問題です。本記事では、なぜ今の20代が経済的にここまで苦しいのか、その背景をさまざまな角度から掘り下げていきます。
2. 賃金は横ばい、物価は上昇:生活が苦しくなるのは当たり前
実質賃金が減り続ける20代
厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、20代前半の平均月収は近年ほとんど伸びていません。それどころか、2022年から続く物価上昇により、実質賃金はマイナスとなっています。
例えば、コンビニの弁当が500円から600円に値上がりし、公共交通機関も軒並み値上げ。電気代やガス代、水道代といったライフラインも高騰しており、生活必需品の支出が増える一方、給与はそのままというのが現実です。
固定費の高さが20代の自由を奪う
さらに問題なのが、家賃・通信費・保険料などの固定費の高さです。都心部に住む20代の中には、手取りの30%以上を家賃に費やしている人も珍しくありません。
また、スマホの通信費や動画配信サービスなど、現代の生活に欠かせないインフラにもコストがかかります。結果として、貯金に回せるお金がほとんど残らないのです。

3. 働いても不安定な未来:非正規雇用と副業時代の到来
正社員=安定の時代は終わった
かつては正社員として就職できれば「一生安泰」とされてきました。しかし今や、大手企業ですらリストラや希望退職を実施し、「転職ありきの人生設計」が一般的になりつつあります。
特に20代は、キャリア初期から正社員としての安定を得られず、派遣・契約社員・業務委託といった非正規雇用の割合が高くなっています。
副業解禁の裏にある「生活防衛」の現実
副業解禁の流れもありますが、それは「収入を増やしたい」からというより、「生活が苦しいから副業せざるを得ない」という人も多いのです。
本業+副業で月収25万円を目指すという声もある一方で、労働時間は増え、体力・精神的な疲弊も深刻になっています。
4. 結婚・出産・持ち家の「コスト」が重すぎる
「普通の人生」が高嶺の花になっている
結婚、出産、マイホーム購入といったライフイベントは、以前なら20代後半から30代前半にかけて実現するものでした。
しかし、現在の20代にとってはそれらは「経済的に不可能」な選択肢です。厚生労働省のデータでも、結婚率・出生率は下がり続け、住宅ローンを組む20代も激減しています。
若者は「持たない生き方」を選ばされている
資産形成が難しい現代において、若者は「必要な時に必要なものを使う」という“ミニマム志向”にシフトしています。
持ち家を持つリスクよりも、賃貸で柔軟に生きることの安心感が優先される時代。これは若者の意識変化というより、「持てない」現実を反映しているともいえます。
5. 若者の経済的困窮をどう変えていくか?
金融教育と制度の整備がカギ
2022年から高校で金融教育が始まりましたが、実際に「生活に役立つレベル」にはまだ達していないのが実情です。
NISAやiDeCoなどの制度も、若者にとっては「遠い存在」に感じられることが多く、もっとわかりやすく、手軽に始められる仕組みの整備が必要です。
社会全体で支援の仕組みを整える
若者の貧困を個人の努力不足と片づけるのではなく、企業・政府・教育機関が連携して包括的な支援体制をつくる必要があります。
住宅支援・奨学金の見直し・就職支援など、親世代では考えられなかった負担が今の若者にはのしかかっていることを、社会全体で理解する必要があります。
6. まとめ:20代の苦しさは社会構造の問題。変えるのは今しかない
今の20代が経済的に苦しいのは、本人の努力不足ではありません。社会全体の構造的な問題が背景にあります。
-
物価上昇と実質賃金の低下\n- 固定費の増加\n- 非正規雇用の増加\n- ライフイベントのコスト増\n\nこれらに立ち向かうには、社会全体の理解と支援が不可欠です。そして、若者自身が「賢く生きる術(節約・金融知識・リスク回避)」を身につけ、声を上げていくことも重要です。
未来は変えられます。その第一歩は、「今の現実を知ること」から始まります。
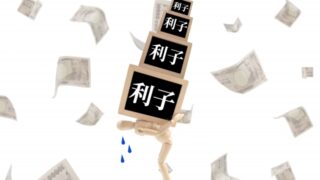
![]() にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
にほんブログ村に参加してます。クリックして頂くと有り難いです。
















